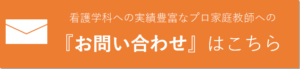総合人間科学部の数学
総合人間科学部(Amazonリンク)は文系学科と、理系学科が混ざっている学科です。
看護は理系学科といえますが、文系と理系の間の位置づけ。
入試形式
上智大学の一般入試(推薦などの総合型以外)には
- TEAPスコア利用方式(全額統一日程)
- 学部学科試験・共通テスト併用方式(学部別)
- 共通テスト利用方式
の3種類があり、2024年1月からの旧課程入試だけでなく、2025年以降も同様の形式をとられる可能性が高いです。
2025年以降は、(看護学科を含む文系)数学ではⅠAⅡBCとなります。
ただし、数B(数列)・数C(ベクトル)なので、範囲はほぼ同じと言えます。
数学は上智の試験方式の変更によって、TEAPスコア利用方式(Amazonリンク)のみで必要になりました。
他2つの試験方式では、数学は共通テストを利用することになります。
共通テストの、分析に基づいた指導をご希望の方はお問い合わせください
オンライン(web)授業も行っております。
3つの大問
総合人間科学部では数学はⅠAⅡBとなっています。
大問は3つで、マーク式の出題となっています。
看護学科分析 → 北里大学 慶應義塾大学 杏林大学 その他の大学分析
看護の中ではかなり難易度が高い
総合人間科学部の中には、
- 教育学科
- 心理学科
- 社会学科
- 社会福祉学科
- 看護学科
の、5学科があります。
看護学科の数学は数学ⅠAのみという大学も少なくありません。
上智は看護の中でも偏差値が最も高い大学の1つ。
ⅡBCも勉強しなければいけないのは高いハードルです。
一方で、他の大学と同様、数学自体の難易度は基礎ばかり。
難しそうに見えて簡単な問題が中心となっています。
ただし、近年の医学科、看護学科への人気上昇を受けて年々問題は難しくなっています。
合格最低点も高くないことを考えると、数学選択は暗記が得意でない生徒におすすめです。
正しい先生に習えば、1年程度本気で勉強すれば十分に合格点を狙えますが、できれば1年半~2年。
遅くとも2年生の夏休みまでに正しい勉強を始めれば、難関看護学科への道はひらけるでしょう。
数学は女子でも避けられない時代
看護だけでなく、総合人間科学部は女の子比率が高い学科ばかり。
男女同権であったり、性が2つではない時代ですが、実際問題として女子生徒が多いという事実があります。
女子生徒は数学に抵抗感がある生徒が少なくありません。
看護はもちろん、教育学、心理学、社会学のどの分野でも数学的思考は必須です。
これは一般企業でも同じです。
数学はどの分野でも役立つ学問です。
そして女の子で数学に強いと、社会でアドバンテージとなります。
是非、女の子だからこそ数学を勉強しましょう。
就職のときも学科試験がある企業は多く数学的要素がふんだんにあるので、先を見据えても有利です。
最初は計算の小問が3問
年によって小問集合が出ないこともありますが、最初は3問の小問集合が出題されるケースが多いです。
2025年1月からの新課程ではある程度傾向が変わるかもしれません。
複素数や対数関数など、数Ⅱの分野から出題されることが比較的多く、
看護学科などをメインターゲットに据えている生徒の場合、数ⅠAばかりで、Ⅱがおろそかになりがち。
数Ⅱの基本計算はしっかりおさえてきましょう。
逆に言うと、複素数や対数関数、三角関数は、王道の基礎計算+典型的問題さえやっていれば十分。
短い時間で対策ができるのでおとくです。
数Ⅱがメインとなっていますが、数Aや数Bからも出題されます。
難しくはないが、単純ではない
全体的に基礎計算から出題されています。
しかし、ただ公式を覚えていればすぐに解答できるわけではありません。
公式理解に加えて、もう一つ難しくは作られているので、しっかりと公式が使えるのはもちろん、例題を数多く解いておく必要があります。
あくまで定期テストで出題されるレベルの難易度なのでそこまで構える必要はありません。
微積は頻出
どの大学でもそうですが、ⅡBが出題される大学では微積は頻出。
上智の総合人間科学部でも、微積は必須といえるほどよく出題されています。
微積は一見難しいですが、数Ⅱの微積はパターンが少なく、覚える公式も多くないので取り組みやすいです。
数Ⅱなのかでは最重要分野なので、優先順位を上げましょう。
典型+ちょいひねり
微積の問題の典型は、関数を微分して図形をイメージしたり、接線を描きます。
そして交点を求めて、面積を積分で求める。これが典型です。
上智レベルだとここに、さらに一工夫。
新しい点を設定し、三角形など図形をもとめたり、何かしらの値を追加する問題が出ています。
問題自体は標準的ですが、典型問題にちょっと加える問題は、典型問題をしっかり理解に基づいて、演習。
そうしてはじめて、ひとひねりに対応できるようになります。
もう一つの大問はAかB
微積ではない大問はどの分野かわかりません。
基本的にはAかBからの出題ですが、数Ⅰを変化させたり、数Ⅱから出題してくる可能性も十分にあります。
ここ数年は確率や場合の数とほかの分野を複合させた問題もよく出題されています。
難易度は他と変わらない
難易度は基本分野を中心にして、そこに少し加えてくるのは変わりません。
だからこそ、最重要はいかに基礎をかためるか、ということ。
数Aであれ数Bであれ、基礎の重要性は変わりません。
特に確率、整数の性質、ベクトル、数列は、典型問題がはっきりとしています。
正しい先生に聞くとわかりますが、数Ⅰなどよりも基礎問題のパターン数が少なく、対策しやすいです。
まずは公式を覚え、それを使いこなすような計算問題から頑張っていきましょう。
対策・勉強法
対策としては特別なことは必要ありません。
文系レベルや看護レベルでは難しいといえますが、総合的に考えると難易度は高くありません。
何よりも基礎レベルを大切にし、公式を使った典型問題を十分に練習していきましょう。
白チャートレベルでも合格は狙える
全体的には白チャート(Amazonリンク)レベルがメインで、それを少し超える問題も出題されています。
満点レベルを目指すのであれば黄色チャート(Amazonリンク)のレベルが必要ですが、合格最低点程度の得点率を狙うのであれば、白チャートレベルでも十分です。
共通テスト対策も有効に使える
共通テスト(Amazonリンク)は、直接受験に使う可能性が高いだけでなく、同様の勉強でで上智の独自試験に対する対策となります。
ただし、共通テストのⅠAと上智を含めた看護のⅠAは形式が異なる部分も多いので、注意が必要となります。
難易度自体は同じくらいです。
ⅡBはセンター過去問でも共通テスト対策本でもどちらでも有効な対策が可能です。
総合的に見ると数Aの優先順位が高い
数Aは大問に出る可能性がそこそこあり、同時に小問集合でもよく出てきます。
特に、確率。
全体のどこかで出題されますし、他の大学でも超頻出分野です。
数Ⅱの計算、微積が最優先事項ですが、その次がこの確率といえるでしょう。
そしてそれに次いでAの整数の性質、Bの2分野(ベクトルと数列)の順番で勉強しましょう。
まとめ
保護者の方へ
上智は言わずと知れた日本の私大で最高峰の一つ。
看護学科や、総合人間科学部のほかの学科も合格するためには一定の努力が必要です。
また、看護などは選択肢も多く、進路指導も綿密にしてくれる先生がおすすめです
上智大学とはいえ、数学においては基礎問題が非常に多いので、現在の数学の偏差値が40を下回っていても普通に合格を狙うことができます。
合格のためには、正しい努力を積み重ねる必要があります。
偏差値40以下ということは、確実に方法を間違えています。
正しい方法を授けてくれるいい先生をお子さんのサポートに用意してあげてください。
早慶上理に合格するための家庭教師なら → こちら
他の記事一覧は → こちら