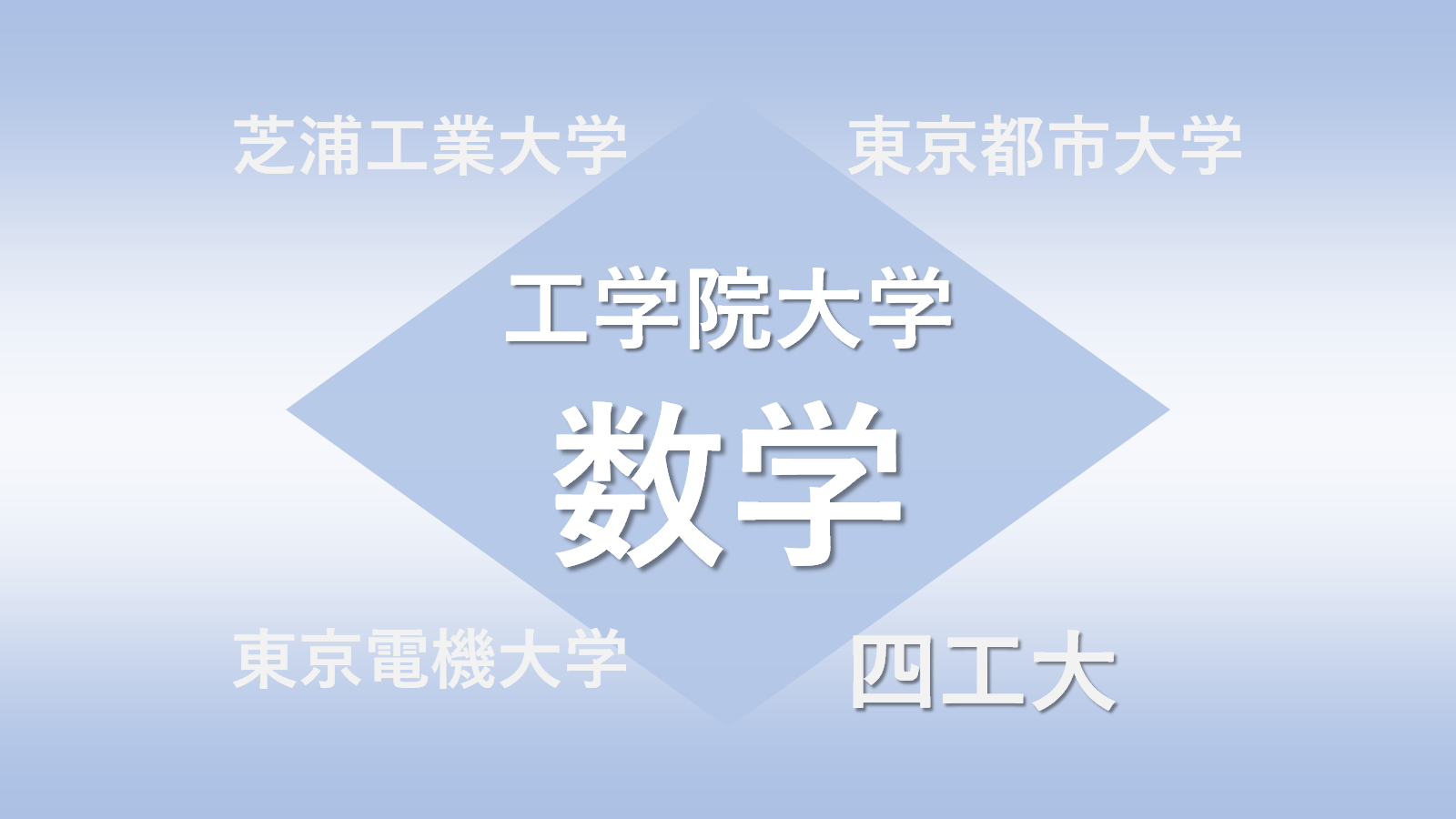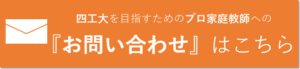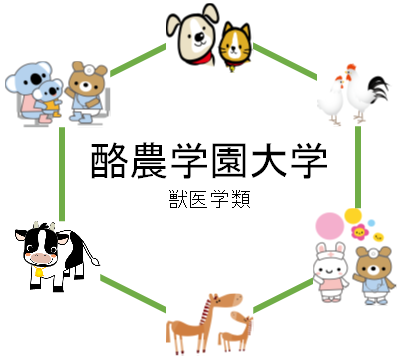工学院大学の数学
工学院大学では主に、
一般選抜
各種推薦選抜
があります。
一般選抜には
S日程(全額統一)
A日程(前期)
英語学部試験利用
B日程(中期)
M日程(後期)
大学入学共通テスト利用(前期・後期)
があり、ここでは最も定員が多く、志望度の高い生徒が受験するメインのA日程の数学を解説します。
A日程だけでなく、S日程だけを受験する生徒にも使えるように作成してあります。
四工大分析
数学は最重要科目の一つ
工学院大学では数学は全学部学科で必須の最重要科目。
2025年からの新課程となり、新しい入試範囲(ⅠAⅡBⅢC)となりました。
試験の難易度だけでなく、合格に加えて大学入学後も考えると、しっかりした理解の習慣が必要になるでしょう。
以下では各学科で定員の多いS日程とA日程の解説になります。
どちらの日程も試験の出題傾向は同じなので、対策も同じになります。
また、M日程では数学Ⅲを含む試験がなく、全学部全学科で数学はⅠAⅡBCから出題されます。
一部学科の試験では数Ⅲをはずすことができる
基本的には数学ⅠAⅡBⅢCが試験範囲となります。
以下の学科では数学Ⅲが除外された、ⅠAⅡBCも選択することができます。
もちろん、数学Ⅲが入った試験も選択することができます。
先進工学部(生命科学科・応用化学科・環境化学科)
建築学部(全学科)
S日程、A日程を含むすべての学科で適用されます。
ⅠAⅡⅢは全範囲であり、B(数列)、C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面)と一般的な理系数学の範囲となります。
試験時間は90分です。
本分析では、数Ⅲありの分析と数Ⅲなしの分析の両方が記載してあります。
ⅠAⅡBCの独自問題は大問4だけ
4つの大問のうち、大問1~3はⅠAⅡBⅢCと同じです。
言い方を変えると、ⅠAⅡBⅢの問題でも、数Ⅲから出題されるのは大問4だけ。
最初は小問集合が4つ
大問は4つで構成されており、最初が小問集合となっています。
最初の小問集合は、公式をそのまま使うような基礎問題が出題されます。
特に数Ⅱから
三角関数
指数対数
は高確率で出題。
図形と方程式も頻出です。
基本的な問題ですが、グラフと絡めてくることもあります。
公式の単純暗記ではなく、本質的な理解を求めていることがうかがえます。
また、共通テストで出題されるような恒等式や不等式といった、他の大学では出題されにくい基礎計算の分野からの出題もあるので、注意が必要です。
さらに絶対値が使われる問題も出題傾向に入っているので、苦手な生徒もしっかり向き合うことをお勧めします。
出にくい問題もある
このあとの大問で必ず出題される微分積分は、小問集合では出題されません。
また、集合と論理、確率、データと統計は、基本的に出題がありません。
新課程となりデータと統計の重要性が高まることから傾向が変化する可能性は十分に考えられますが、現時点では数Bは理系数学の範囲でも文系数学の範囲でも範囲外となっています。
場合の数と確率や数学と人間の活動(旧:整数の性質)は毎年ではないものの、一定量は出題されます。
もし工学院のみを受験する場合には確率の優先順位をおとしてかまいません。
ただし、実際には工学院以外も受験するでしょうから、場合の数・確率の勉強は怠らないようにしましょう。
プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら
オンライン(ウェブ)授業のご説明は → こちら
全記事一覧は → こちら
大問1が解けないと次に進めない
4つの大問で、圧倒的に大問1が簡単であり、基礎計算となっています。
そもそも大問1で4問中3問解けないようであれば基礎力不足。
まずは公式を確認し、大問1をほぼ100%解けるようになってから次の大問のことを考えましょう。
正しい先生と一緒に勉強すると、数学が苦手・自信がない生徒でも大問1はほぼ満点がとれます。
大問2,3は数B・Cからの出題が必須
2つの大問のどちらかは確実にベクトルか数列から出題されます。
また、年によってはどちらも出題されることがあります。
本気で合格を狙うのであれば、ここで一定の点数が必要です。
数列とベクトルは小問集合でも出題されることがあり、他の大学でも出題頻度が高いです。
片方が数B・Cで、もう一方が数Ⅱの可能性が最も高いですが、過去問には数Aの数学と人間の活動(旧:整数の性質)でよくある証明問題がでたこともありました。
証明問題はほぼ出題されていませんが、過去に出題歴があることから0とはいえません。
現実的には、数学と人間の活動も大問としての出題比率は非常に低いです。
優先順位は大きく落として大丈夫でしょう。
数B・Cも標準レベル
数列もベクトルも難易度が標準的。
バランスよく出題されています。
数列は漸化式に偏らず、基礎の等差数列や等比数列をしっかり理解していることを問うこともあります。
また、ベクトルも平面もあれば空間もあり、ベクトル方程式も出題されます。
![]()
もちろん全て典型問題なので、普通の問題集をもれなく勉強すれば、必ず見たことのある問題になります。
数B・C自体は数Ⅱよりもパターンがわかりやすく、取り組みやすいです。
質の高い先生の授業を受ければ確実に点になります。
最後は微積
数Ⅲがある学科でも、数Ⅲがない学科でも、最後の問題は微積からの出題になります。
数Ⅲは微積以外いらない
数Ⅲは極限も範囲内。
また、数Cになった複素数平面はかつて数Ⅲの一部でした。
新課程の現在も、工学院対策としては微積のみで大丈夫です。
また、他の四工大でも微積の出題率は100%であることから、どの大学を受験するにしても数Ⅲの微積は確実におさえましょう。
大問2,3と同様に基礎~標準レベルの典型問題から出題されます。奇問難問はでないので、とにかくどの問題集でも載っているようなタイプを完璧に仕上げるのが第一です。
計算量は決して多くありませんが、最後の積分計算で面積を求める場合には、多少の計算量があります。
正確にできるよう、しっかり訓練しましょう。
数Ⅲの微分は一定の難易度があるが、そこまで難しくない
工学院大学の数Ⅲは、基本的に標準レベル。
白チャート(Amazonリンク)である程度点数がとれてしまうので、合格最低点を目指すのであれば無理に黄色チャートを使わなくても大丈夫。
青チャートは絶対に不要です。
数Ⅲがない微積は共通テストレベル
数ⅡBCまでの試験も、これまでと同じようなレベルです。
そして出題も数Ⅱの微積からと決まっています。
黄色チャート(Amazonリンク)と共通テストレベル(センター過去問)をしっかり勉強することで十分な力がつきます。
レベルでは共通テスト程度ですが、問題形式としてはセンター過去問が有効です。
問題集
基本的には「黄色チャート」で対応できます。
前述したとおり、数Ⅲは白チャートでも問題ありません。
芝浦などを受験する場合は、黄色もしくは青が必要ですが、芝浦以外の四工大であれば黄色で確実に合格できます。
公式理解に関する記述がないことから、お勧めはしませんが、レベルとしては学校で配布されることが多い4STEPも使えます。
また、センター過去問(Amazonリンク)や問題集も非常に有効です。
一方で共通テストとは毛色が違うことから、共通テスト系の問題集は効率的とは言えません。
特にⅠAは驚くほど合っていないので、国公立を受験しないのであれば使わないでください。
基礎公式を一通り勉強したあと、チャートなどで基礎~標準の典型問題を2周やりましょう。
その後センター過去問を5~15年分勉強しましょう。
追加で数Ⅲの微積の白チャートなどを一通りやれば、赤本にチャレンジする資格が十分に手に入ります。
数Ⅱと数BCがかぎ
数Ⅲはもちろん重要ですが、比率が低く、最重要なのは数ⅡBCです。
特に微積と数列・ベクトルは入念な準備が必要です。
できれば高校2年の終わりまでに一通り勉強をして、センターレベルが7割くらいは解けることが理想です。
重ねてになりますが、共通テストではなくセンター過去問を使ってください。
もちろん、難易度が基礎の問題もおおいので、正しい勉強法をすれば高3から対策をしても間に合うでしょう。
まとめ
- 公式暗記は最低条件、理解まで進むのが理想
- センター過去問をうまく使おう
- 数Ⅲは微積のみでOK
保護者の方へ
工学院大学の数学は、四工大でも比較的取り組みやすく、同時にお子さんが勉強法を間違えやすくなっています。
受験生は難しい大学や、難問を解きたがります。
特に浪人生や男子生徒ではよく見られる傾向があります。
自己分析があまり得意ではないお子さんの場合は、保護者の方がしっかりしたフォローされるか、いい先生を用意するだけで数学はもちろん、全体的な合格率が大きく高まるでしょう。
人気がある四工大だからこそ、入念な準備をしましょう。
四工大に合格するための家庭教師なら → こちら
他の記事一覧は → こちら