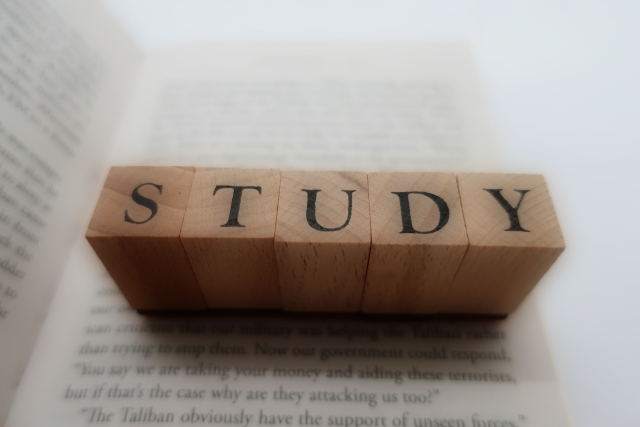保護者は進路の重要性がわかるのに、子供に伝えきれない
高校1年生の終わりになると、生徒と親御さんと必ず話すことがあります。
文系理系の選択(文理選択)についてです。
(この問題は、大学選びにも共通しています)
その時に必ず出る話題が、
数学が苦手なので文系がいいのでしょうか?
暗記が苦手なので理系がいいのでしょうか?
といったことです。
動き始めはいつか?
実は、高校1年生の終わり時期にこの悩みを考え始めるようでは遅すぎます。
一般的なレベルでの理想論を言えば、高校1年生での夏休みからです。
そのためには、保護者の方が率先して高校1年生の6~7月から徐々に考えるよう、お子さんに呼びかける必要があります。
私の生徒で高校1年から指導を始めた場合は、高校1年の夏休みが進路を考え始める時期になります。
私の指導では、必要なタイミングで2者面談と3者面談を何度も(1か月かけて毎週のように話すときもあります)繰り返す生徒もいます。
逆に1~2回でさっと決まる生徒もいます。
具体的な進路相談の進め方は → こちら
この時期からスタートすれば、冬にくる文理選択はしっかりと自分の考えを持った上で落ち着いて決断ができます。
そもそも論になりますが、現在は文理選択という考え方自体への疑問があり、その流れは加速しています。
本当の理想はもっと早い時期から
実際私の生徒では、中学受験する場合は小学生の時からそういう話をします。
小学生の時に文系理系を選択するためではありません。
本人の興味の方向性を、家庭教師である私が理解するだけでなく、本人と保護者の方に理解してもらうためです。
また、興味の理解をすることで、いろいろな夢を持ちやすくなり、本人の可能性を広げることができます。
決定する必要はありませんし、時間をかける必要はありませんが、意識づけをしていきましょう。
この意識づけと長期視点は大人になってからも役立ちます
中学受験生や高校受験生の場合、学校を選ぶ基準も本人の学力だけでなく、やりたいことや思考傾向によって変わってきます。
進路指導もついているプロ家庭教師へのお問い合わせは こちら になります。
進路は自分の中から選ぶ
先ほどの問いかけである、「うちの子は文系と理系のどっちにいくべきなのか?」ですが、答えは明白です。
数学や暗記は進路選択における本質ではありません。
本人が何をしたいのか? から進路を選びましょう、ということです。
つまり、数学が得意かどうか、暗記が得意かどうか、は考えの助けになりますが最大の検討ポイントではありません。
そう、文系理系の選択であれ、大学選び、学部や学科選びも基本的には同じです。
「子供が何をしたいのか」 これにつきます。
この話をすると、親御さんからよく言われるのが、「うちの子は特にしたいことがないんです。」
これも間違いであることが多いです。
実際私が生徒と話してみて、将来の明確な夢がなくても、興味があることやこういったことをもっと知りたいという内容は必ず出てきます。
この時の興味が、理系ならば理系に進学し、文系ならば文系に進学すればいいだけです。
もちろんスポーツや芸術ということもありえます。
お子さんは想像以上に進路のことを知らない
大人たちが当たり前と思っていることを、お子さんは基本的に知りません。
大学の名前どころか、そもそも大学が何をするところなのかイメージできていません。
学部や学科になるとさらに知りませんし、なんとなく親に言われたから○○学科は知っている、という程度です。
そして、保護者の方の多くも、現在の大学生や就活生などがイメージ出来ていないことが非常に多いです。
保護者の方は、ご自分が進路を選ばれた時代、大学や就活時代がイメージに強く残っているケースが多いです。
現在は20~30年前と同じ部分もあれば、相当違う部分もあります。
お子さんと一緒に、現代の学生が進路を選ぶということを学ばれることをおすすめしています。
(希望されるご家庭には、私が実例を交えてご説明します)
科目から選ぶのは、自分の中から選びきれないときだけ
最初に否定しましたが、科目から選ぶ方法もあります。
なぜならば、好きな科目は興味が強いことが多く、進路に強く影響するからです。
また、高校の難しい科目を2年間、大学ではさらに難しい内容を学ぶので、好きか嫌いかは重要です。
高校2,3年、大学、大学院(修士)と考えると、8年です。
もちろん博士号取得まで考えると10年以上。
苦手な教科を長く続けるのは確実に苦痛です。というより不可能に近い。
ですので、科目も考える要素になります。
他の記事一覧は → こちら
実例
私の実例をご紹介します。 私自身は理系を選択しました。
大学が生物系だったのが最大の理由ですが、実は法律関係とも迷っていたのです。
生物系なら理系。法律系なら文系です。
生物系に関して学びを深めたい
生き物にかかわる仕事をしてみたい
ということで生物系が第一志望であった、ということが決定打でしたが、科目も考えて総合的に選びました。
実は、高校2年の途中までは生物を本格的には勉強しておらず、途中から生物のクラスに入れてもらったという経緯もあります。
学校によっては途中変更を受け入れてくれますし、学校が受け入れてくれなくても複数科目を指導できる先生がいれば、簡単に新しい科目の対策ができます。
それ以上に大事なのが、広い視野を持っている先生である可能性が高いということです。
私も苦手教科・分野で悩みました
総合的には、暗記が苦手であり嫌いだった要素が入っています。
暗記が重要な、古典・社会は学びたくありませんでしたし、受験上でも不利というのは、選択の1つの要素になりました。
逆に、数学や化学・生物が好きだったというのも、もちろん一因となりました。
余談ですが、学生時代嫌いであった社会(日本史・公共・公民など)を今は生徒に教えることもあります。
学びなおしてみると楽しい部分も多く発見できました。
注意してほしいのが、大学受験という意味では暗記は多いですが、法律系は暗記ばかりではないということです。
法律系で最も重要なのは基本的には論理的思考力だからです。
ですので、高校1年の終わりのときの私の第一志望が法律系であれば、おそらく文系を選択していたと思います。
(大学受験まで古典と歴史は頑張ろう、2年頑張り、大学に行けば古典や歴史は勉強しなくていいから、ということです。)
決定の順番を整理すると
- 生き物にかかわる仕事に興味が一番ある
- 生き物なら生物系の学科
- 生物系に行くなら理系。数学と理科を長く勉強することになる。
- 理系の科目は好きだし、得意
- よし、理系にしよう
という流れでした。
私が指導してきた生徒
今まで私が指導してきた生徒の興味は多岐にわたります。
具体的には、医療系、生物系、文学系、芸術系、IT系、観光、工学、文化学、心理学、スポーツ…
若いほどコロコロ変わりますが、どのような興味に対しても、それにあった職業はあります。
また、今は新しい職業を作ることも可能です。
子供の夢はどんどん変わっていいのです。
それは可能性、つまりは本人の世界の広がりを意味しています。
ですから、まずは自分の興味をより深堀できることを、進路を考えるファーストステップとしてください。
今はウェブ授業でも生徒の進路相談だけでなく、保護者の方との面談もやりやすくなりました。
好きな科目嫌いな科目はその次以降に考える要素です。
私が指導している生徒は、こまめに進路の話をしています。
進路指導もついているプロ家庭教師への お問い合わせ はこちらになります。
進路選択のまとめ
- おこさん(自分)が何をしたいのか?が最重要
- 嫌いなことは興味が多少あっても長続きしにくい
どこよりも綿密な進路相談を行うプロ家庭教師は → こちら
他の記事一覧は → こちら