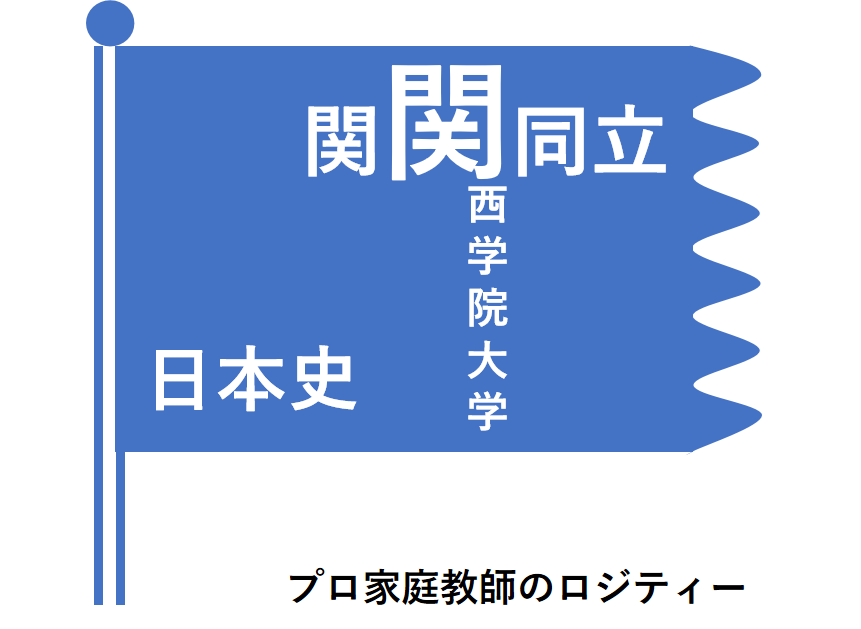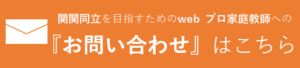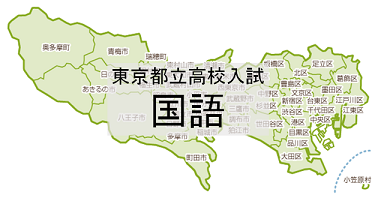関西学院大学の日本史
関西学院大学における主な入試形態(一般入学試験)は、
全学部日程
学部個別日程
共通テスト併用日程
英数日程(実施がない学部もあり)
の4種類。
理系と文系で若干異なるので注意が必要です。
定員のほぼすべてが一般入学試験(全学部日程)なので、対策すべきはこの一つとなります。
本分析でも、全学部日程の日本史にターゲットを絞って分析しています。
関西大学分析 → 化学生命工学部 環境都市・理工学部 理系数学分析
試験時間は気にしない
問題数は40問で、時間は60分。
全問選択式であり、1問にかかる時間は限定的です。
試験中に悩む問題もあるでしょうが、全体で見て時間が余る人は多く、不足することはほぼないでしょう。
正確な理解が合格できる暗記をつくる
関西学院の日本史は選択式ですが、選択肢の中に正解は一つとは限りません。
選択肢の構成は問題ごとに違いますが、複数正解があったり、全ての選択肢が間違いということもあります。
いかに正しい暗記をするか、が必要となりますが、ただ単純に暗記をするというものではありません。
日本史の膨大な暗記には有効な勉強方法があり、1年以上前の暗記を長期記憶に定着させるだけでなく、前後の関連性とつなげる必要があります。
単純暗記ではなく、理解の日本史を基本としていきましょう。
歴史総合は範囲外
日本史は全学部日程でも学部個別日程でも歴史総合がありません。
日本史探究・世界史探究が範囲となりますが、地理が選べる場合は地理総合・地理探究が範囲となります。
全学部では社会(日本史・世界史・地理)もしくは数学から1科目。
学部個別では社会(日本史・世界史)もしくは数学もしくは国語(漢文なし)から2科目。
文系受験の生徒は国語と社会から選択しがちですが、経済学部などの生徒は日本史と数学という選択もおすすめです。
配点は必須科目200点で、選択科目150点なので、日本史は全学日程でも学部個別日程でも150点の配点となります。
公共・政治経済は一般的には多くの大学の一般入試で利用可能ですが、関西学院大学では利用できないので注意してください。
共通テスト利用であれば、公共・政治経済も利用可能です。
一般選抜(全学部日程・学部個別日程)で日本史が入試に必須の学部
なし
一般入試(全学部日程・学部個別日程)で日本史が選択できる学部
神学部
文学部
社会学部
法学部
経済学部(文系型)
商学部
人間福祉学部
国際学部
教育学部(文系型)
総合政策学部(文系型)
大問1は全ての時代から10問
大問1は10問。
全ての問題で2つの1文があり、それぞれの〇×を性格に問われる4択となっています。
標準的な知識を問われ、政治や戦争、文化などが時系列順に出題されています。
典型的な一問一答
選択肢としてはa、b、両方〇、両方×と四択ですが、一問一答の集合体ともいえます。
各問題で関連性はなく、aとbも時代はほぼ同じですが、別知識といえるでしょう。
大問1のために特別な勉強は不要であり、以下の大問2~4や併願校の対策をしていれば自動的に大問1対策となります。
古代からもしっかり出題
大問2~4も10題ずつ出題されます。
全体の比率でいえば江戸時代以降が中心ですが、原始や古代と言われる西暦700年以前からも出題があります。
大問2の傾向を知ることは合格に近づく
大学によっては新しい時代の方が現代に役立ちやすいこともあり、古代の出題が明確に少ないことも多いです。
また、法制度や教育、信仰や災害などのテーマを決めて全ての時代から出題されることもあります。
大問1も大問2も幅広い時代から出題されやすいので、深さはそこそこでも広さはしっかりとした学習が求められます。
関学では大問2に古代や律令国家成立時の範囲を含むことが多くなっています。
時代を一気通貫する様な出題出ない場合は、古代~近世くらいが中心で出題されます。
大問3は江戸~近代
大問3や4は典型的な日本史の問題となっています。 文章による史料が添付されており、 近代が基本ですが、室町や戦国は時々出ており、江戸時代の初期から宿題されることもあります。 室町以前が一部出題されることもありますが、分量は少なめです。
ABの2部構成
基本的に時代順番の出題であり、Aが5問、Bが5問です。
Aは江戸時代で、Bは幕末や明治以降が最も多いパターンではありますが、年によって変動するので全時代の勉強は必須です。
難易度は標準的な知識問題ですが、江戸以降は暗記項目が多くなるので単純暗記で関学レベルの深さまで修得するのは至難の業といえます。
歴史の流れを理解する正しい勉強法がおすすめです。
よくある質問・料金などは → こちら
web授業に関しては → こちら
大問4は近現代
大問4も大問3と同様に文章による史料が与えられています。
大問3のようにABの2部構成になっていることが多いですが、過去には分割されていない10問通しの時もありました。
時代は現代が中心である以外は、傾向や難易度も含めて大問3と同じとなっています。
ただし、大問3で近代以前が多い出題の場合は、大問4でも近代から出題されることも多くあります。
大問3が室町・戦国~近代(第二次世界大戦まで)
大問4が近代(幕末くらい)~現代
基本的な勉強法、テキストの難易度
関西学院大学は、標準レベルの知識が中心ではありますが、範囲が広く受験における標準レベルをほぼ完璧にするのはかなり時間がかかります。
標準レベルくらいならなんとかなる、という勘違いをする生徒が多いですが、そういった甘い考えで合格することはほぼないでしょう。
やみくもに暗記しようとするのではなく、まずは流れを理解しましょう。
古代などはどうしても流れを理解するより単純暗記になってしまうのは事実であり、平安の中期くらいからは流れの理解がしやすくなります。
重要性を考えても、場合によっては最初は平安くらいから勉強をスタートさせて、学校よりも先に行き、最後に古い時代を暗記していく作戦もあります。
流れの理解とは関連付けること
単純暗記と、理解の暗記の違いは関連性です。
一つの出来事と、近しい出来事をいかに関連付けるか?がポイント。
一問一答形式ばかりで勉強していると、関連付けの習慣がつきにくいので、最初に一問一答をすることはおすすめできません。
あえて細かくない参考書をつかう
有名な山川のテキスト(Amazonリンク)などはよくできていますが、一つ一つが細かく関連性を自分で整理するのが難しいです。
時代や流れを重視していたり(Amazonリンク)、共通テストや学校の定期テストをメインターゲットにした本(Amazonリンク)を最初によんで、流れの理解とイメージを作りましょう。
まとめ
保護者の方へ
関西学院大学の日本史は、流石関学と思わされる様な難易度。
極端に難しいわけではありませんが、時間をかけて努力を積み重ねつつ、自分で勉強方法を工夫した生徒が有利になるようなレベル設定と出題形式になっています。
遅くとも高校2年生の春くらいには受験の準備に取り掛かることをおすすめします。
ただ塾に入れて勉強されるのが悪いとはいいませんが、勉強方法を工夫するには試行錯誤が必要であり、塾から一方的に教えられる方法は生徒自身の自己分析力が高いことが前提となります。
お子さんの自習や自己分析力に自信がない場合は、双方向で話がしやすく、日本史の内容よりも勉強方法についてアドバイスできる人が必須でしょう。
いい先生を探すことは、保護者の方ができる最高のサポートかもしれません。
勉強方法を工夫しながら理解の日本史が身につくプロ家庭教師に → お問い合わせ
他の記事一覧は → こちら