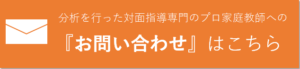東京女子大 文学部の日本史
東京女子大学の主な入試としては、
- 個別学力試験型
- 英語外部検定試験利用型
- 大学入学共通テスト(3科目型・5科目型)
- Global Citizenship Program Link型
などがあります。
以下ではメインである個別学力試験型(英語外部検定試験利用型含む)に関する解説となります。
日本史の範囲は日本史探究のみ。
歴史総合は範囲外です。
ただし、共通テストは歴史総合必須。
また、ほかの大学では歴史総合が範囲内になることも多いので、併願校や試験方式を考えるには綿密な進路相談など準備が必要です。
科目が増えたり、変わると、勉強スケジュールが大幅に変更になります。
高校3年生からでは間に合わない可能性が高いので注意してください。
日本史(社会の選択)が選べる学科
東京女子大学(現代教養学部のみ)で社会が必要なのは、
- 人文学科
- 国際社会学科
- 経済経営学科
- 心理学科
- コミュニケーション学科
です。
日本史探究、世界史探究、数学から1科目選択となりますが、私立の文系学科ということで、多くの生徒が日本史か世界史を選びます。
時間は余裕がある
大問が4つで60分。
![]()
全ての問題が単語の記述か選択問題となっています。
文章の記述が一切ないので、時間を気にする必要は一切ありません。
難易度は高くない
記述がなく、全体の知識レベルも基礎が多くなっています。
出題範囲も絞りやすく、点数がとりやすい構成です。
ただし、合格最低点が高めなので難しくない問題を落とすことなく正確にこたえなければいけません。
各大問と出題範囲には傾向がある
大問は4つありますが、
古代と中世から1~2つ
江戸時代から1つ
近現代から1~2つ
と決まっています。
日本史の入試問題としてはよくあることですが、出題範囲は江戸時代以降の比率が高いです。
他の大学同様に、しっかりと漢字で用語が書けること。
1問1答に対応できることが必要ですし、地図と対応させた勉強も求められます。
図表の出題は少ないですが、毎年1~2つ程度は見られており、油断はできません。
大問1が一番難しい
大問2以降は出題範囲が絞りやすいですが、大問1は江戸時代より前から確実に出題されますです。
その中での一時代を切り取られて出題されるので、網羅的な勉強が必要です。
比較的出題頻度が高いのは奈良~平安時代前後の政治
他にも鎌倉時代以降のみが出題されているため、原始の勉強は完全に後回しにしましょう。
設問の聞き方や必要な知識は他の大問同様に基礎~標準なので、特殊な勉強は必要ありません。
江戸以降を勉強した後に、丁寧に一つ一つ知識を増やしましょう。
江戸時代はほぼ確実に出題される
江戸時代も基礎~標準の知識が求められます。
近代は1800年代の開国と幕末から始まります。
江戸時代のメインは近世となっているので、近代から勉強を始めると江戸初期~中期の勉強が不足します。
東京女子大では、江戸時代の開国以降は比較的出題率が低く、開国前までが重要になります。
ですので、大学別対策としての勉強は江戸時代(1600年の関ケ原~)からはじめましょう。
ただし、併願校と志望度によって勉強のポイントが変わるので、現実的には江戸以降だけ勉強すればいいということにはならないでしょう。
近現代を正しく勉強
大問3と4はほぼ確実に近現代から出題されます。
言い換えれば、近現代が完璧に近ければ40点以上は保証されるともいえるでしょう。
大問3は幕末~明治~大正
3つ目の大問では幕末~明治による近代化の出題が多くなります。
過去には文化中心の大問が出題されるなど、歴史の流れ以外の部分でも勉強が必要です。
他の大問同様に、基礎を大切にしていきましょう。
大問4は戦後が多い
最後の大問で最も出題頻度が高いのが、戦後の昭和と平成。
もちろん、第2次世界大戦前が出題されることもありますが、戦後の日本が圧倒的に出題されています。
多くの大学では大戦直後から日本が復興していく経済政策を中心に出題されますが、2017年には平成に関する出題もありました。
令和になり、平成は歴史へとかわりつつあります。
実際のテストでは日米関係しか聞かれていませんが、今後5~10年すると日中、日亜の出題があるかもしれませんね。
参考書・問題集
単語の記載が多い、ひとつひとつを丁寧に暗記していくことが求められます。
時代の流れを理解できることが理想ですが、基礎知識の定着も大切。
残り時間を考えて効率的に学習をすすめましょう。
特に浪人生はいきなり問題集に取り掛かる傾向にあります。
まずは参考書をきっちり読んでインプットに時間をかけましょう。
インプットが終わったら、問題集を解いて知識の定着を図ります。
とくに江戸、明治、昭和には時間をかけたいです。
基礎~標準レベルの問題集。
知識レベルは共通テスト・中堅私大向けです。
国公立向け、難関私大向けの問題集を触る必要は全くありません。
まとめ
- 江戸以降からはじめよう
- 奈良時代より前は後回し
- 基礎を大切にしよう
東京女子大を本気で目指すなら → こちら
他の記事一覧は → こちら