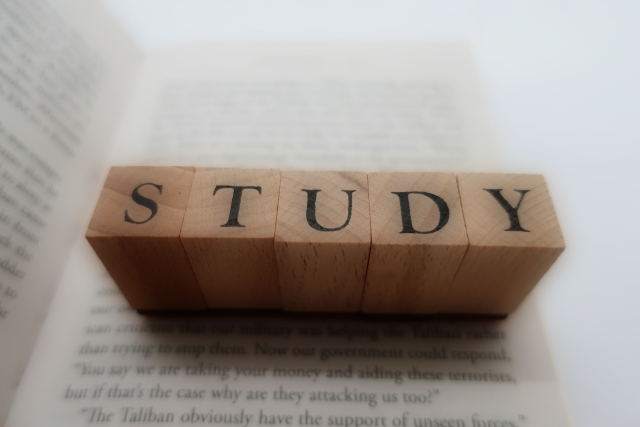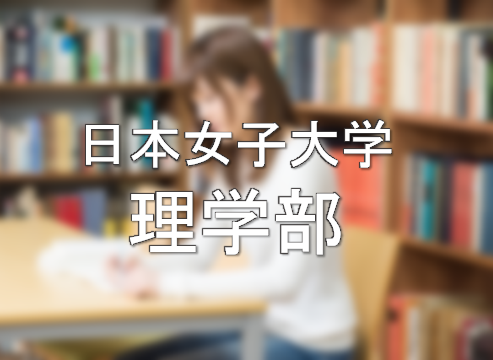日本大学(N方式)の英語
N方式は全学部で問題が同じ全学部統一の方式。
学部別で問題が異なるA方式とは別の方式となっています。
英語はどの学部の受験でも利用でき、下記を見てもわかりますが、ほぼすべての学部学科で必須の科目となっています。
もちろん医学部や獣医学科でも必須です。
ただし、N方式は定員が少ない方式であり、日程にも注意が必要です。
N方式で英語が使える学科
【外国語(英語)が必須の学部】
法学部・文理学部・経済学部・商学部・芸術学部(写真学科・映画学科・他)、国際関係学部・危機管理学部・スポーツ科学部・理工学部・生産工学部・工学部・医学部・歯学部・松戸歯学部・生物資源科学部・薬学部
『外国語(英語)が選択の学科』
芸術学部(美術学科・デザイン学科)
すべての学部学科の生徒が受験する可能性があるからこそ、問題形式は幅広く、難易度も比較的簡単になっています。
GMARCH分析 → 明治大学 立教大学 中央大学 法政大学 学習院大学
基本的にはだいたい方式は同じですが、2025年1月から新課程となります。
問題形式や難易度に左右されないように、本質的理解を前提とした勉強をおこないましょう。
合格最低点などの日大医学部の情報は → こちら
医学部の学部別入試(A方式)の数学は → こちら
日本大学の生物資源科学部、獣医学科は → こちら
大問1,2は似ているようで違う
一見すると、どちらもよくある4択の文法問題のようですが、実は違います。
少し古いですが、2019では最初に内容理解の長文読解が出題されました。
近年は長文が最初に出ることはなくなっています。
大問1は、いわゆる文法問題
助動詞や疑問視、前置詞に動詞の活用など、学校の文法の授業で習うような分野に関する問題です。
難易度は基本的な問題が中心。
旧センターレベルより少し簡単な問題がよく出ます。
共通テストでは文法に特化した問題はなくなりました。
私大の文法対策にはセンター過去問が有効でしたが、問題集がへりました。
中堅私大向け、もしくは文法に特化した問題集がおすすめです。
大問2は、単語力
ここでは、文法問題のように見せかけて、実は単語力と熟語力が重要になってきます。
文法は動詞に関する問題が中心ですが、ここでは動詞だけでなく、名詞や副詞など様々な単語がきかれます。
文法のような変化はなく、似た意味の単語を文に合わせて選択します。
類義語や対義語などは集中的に勉強しましょう。
ただし、難易度はそこまで高くなく、標準レベル。
共通テスト用の単語帳(Amazonリンク)やターゲット1400(Amazonリンク)などをしっかり仕上げれば高得点を取ることができます。
英単語の勉強法なども見て、まず初めに勉強しましょう。
大問3は年によって違う
大問3はアクセントであったり、動詞や熟語も出題される文法だったり、年によって違います。
近年は熟語やそれに近い形が多く、文法や語彙の問題となっています。
ただし、大問1,2の勉強を正しく行っていれば、単語の延長上でアクセントの勉強はしていますよね?
日本大学の医学科や獣医学科を目指す場合は広範囲な勉強が正しく出来ているはずです。
特別大問3のために何かをする必要性は低いと言えます。
それ以外学部学科を第一志望とする生徒は、一定の対策が必要でしょう。
英単語の勉強法は間違えると無駄が非常に大きくなるので、注意してください。
大問4は、会話文と短めの長文
年によって違いますが、会話文と短めの長文がこの中盤で出題されます。
近年は長文中の空欄に対する穴埋めが出題されやすいです。
過去には2問の会話文が出題されていました、減少傾向。
アクセントの出題があった年もありましたが、近年では出題されていません。
空欄補充であれば、読解力と単語力が共通テストレベルまであればそこまで難しくありません。
一定の練習は必要でしょうが、特別新しいことは必要ないでしょう。
よくある質問・料金などは → こちら
web授業に関しては → こちら
会話文は日大では定番
医学部では会話文が高確率で出る大学は限られていますが、日大英語では会話文はおなじみの出題です。
ただし、文章量としてはあまり多くなく、また会話表現が特に狙われるというわけではありません。
ですから、形式としては会話文ですが、短めの長文に近いイメージをもって過去問に取り組むとやりやすくなります。
![]()
レベルとしては共通テストレベルの長文の内容理解ができていれば、十分に解答を選ぶことができます。
会話文は大問4で出題されたり、大問6で出題されたりするので、どこで出てきても驚かないように、時間配分を間違えないように練習しておきましょう。
私大の長文対策の中で会話文に関してもいくつか練習をしておくのがよいでしょう。
医学部受験において、日大N方式のための会話文対策は重要度が低いです。
時間を割きすぎないように注意しましょう。
短めの長文は300語程度
日大は各学部でそもそも長い長文をあまり出題しません。
逆に短めの文を複数出題することがよくあり、このN方式でもほぼ確実に出題されています。
長文の難易度自体は共通テストレベルかそれよりも簡単なレベル。
また、内容把握ではなく、長文内に設定された空欄に当てはまる単語を選択するタイプ。
長文全体を読まなくても、前後の文章の意味で正解を選ぶことができます。
接続詞などの単語中心なので、ここでも単語力が重要。
共通テストレベルの単語は最低でも90%、できればほぼ100%の習得をしておきましょう。
大問6か7がメインの長文
この大問では500語程度の長文があり、問題はすべて内容把握に関する選択問題です。
過去では大問1や5で出題されたこともあります。
また、接続詞や熟語の短い長文が出題されることもあります。
2022など大問が8つになっている年もあるので、注意が必要です。
長文の難易度は共通テストの最後の大問と同じくらいですが、文章が短い文難易度は高くありません。
単語や熟語としても共通テストレベルで大丈夫。
全体としては大問5,6が難易度が高いですが、それでも解きやすいので取り組みやすいです。
順番が前後することもあるので、試験うけるときは、最初の1分で解答順を明確にしておきましょう。
対策のまとめ
- 日大はA方式をメインで考えよう
- N方式は共通テストレベルが部分的に使える
- N方式だけでなく、他の大学への対策になる根本的学習をしよう
保護者の方へ
N方式は難易度が標準的ですが、出題形式が幅広く総合的な英語力が必要となります。
また、医学科や獣医学科をN方式から狙うのであれば高得点が必須。
お子さんの現在の学力と、日大への志望度、学部学科によってかなり変化します。
そして、日大を受験する生徒の多くが英語の勉強方法を間違えているせいで、非効率な対応になっています。
保護者の皆さんがお子さんのズレに気付き、いかに早く対応できるかが合格を左右するでしょう。
プロ家庭教師の指導に興味がある方は → こちら
他の記事一覧は → こちら