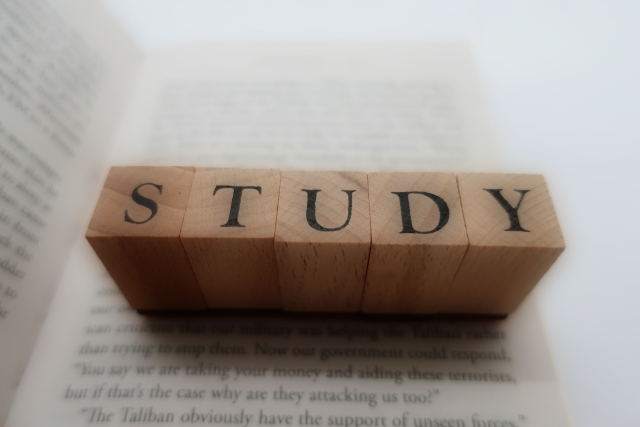勉強は時間より質が大事
以下の記事で勉強時間の目安を示しますが、あくまでわかりやすい基準として時間を示しています。
時間ばかりにこだわるのは本質的ではない(Amazonリンク)ので注意してください。
本質的な勉強や習慣は、大人になっても役に立ちます。
逆に言えば、大学生や社会人になってからを想定していない勉強や指導は効果が半減しているといえるでしょう。
本質としては理解という成果にこだわる
成果 = 質 × 時間
なので、勉強時間だけあっても意味がありません。
王道の勉強をすることで、自分の勉強の質を高めましょう。
私の生徒では、質を優先し量は本人に合わせるところからスタートすることが多いです。
学習計画に目安はありますが、生徒一人一人の特性に合わせることが理想的であることは間違いなく、集団指導よりも個別指導の方が実行しやすいです。
量でコントロールするのもオススメ
勉強は時間ではなく、1日当たり、1週間当たりの量を決めておく方がよりよいです。
例えば平日は、
英語と数学の問題集を2ページ
理科と社会のワークを授業で進んだ分だけ
といった具合です。
とりあえず学校の宿題だけ、というのは危険です。
私の生徒には、基本的に宿題は量で出していますが、一部の生徒には勉強時間で出しています。
1年生は毎日1時間
中学受験をしていないと、勉強習慣がつかないまま、勉強習慣がついていないお子さんが多いです。
中学受験をしていると、頑張った反動で勉強から離れて、再び勉強を頑張るきっかけがつかめていないお子さんも多いです。
最初は勉強習慣をつけると同時に、正しい勉強法を身に着けるチャンスです。
理想は中学入学前に十分な備えをすることですが、中学1年生のうちであれば問題ないでしょう。
目標は習慣化
平日は1日30分~1時間は勉強する習慣をつけることを目標としましょう。
ただし、無理しすぎたり、絶対1時間しないといけない、といった厳しい制限は不要です。
目標は毎日かならず1時間勉強することではなく、
日々勉強することが当たり前になっているということです。
学校の宿題は正解か
とりあえず学校や塾の宿題を提出していれば安心だと思っていませんか?
偏差値が60を下回るお子さんの場合、半分くらいの生徒が勉強法を間違えています。
そして、正しい勉強法・自分にあった勉強法について考えずに、言われるがままに勉強をしています。
これでは本質的な、社会人になっても活かせるような勉強法が身につきません。
集団塾も学校も、多くの先生は一人一人の勉強法まで把握していません。
そもそも宿題もハンコを押すだけで内容までチェックしていない場合も多いです。
宿題をしているだけでは、かなり危険です。
学校任せ、塾任せにしすぎず、余裕があるタイミングでいいので、お子さんの勉強を確認してあげましょう。
プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら
オンライン(web)授業も実施してます。
休日はどちらかで1時間
土日のどちらか、せめて1日はしっかり勉強できる時間をとりましょう。
しっかりと言っても1時間あれば大丈夫。勉強熱心な子や目標が明確な場合は2~3時間あるとよいでしょう。
部活や遊びの機会が多い生徒でも、土日は完全に遊ぶという習慣はおすすめしません。
運動部で試合が丸一日ある生徒でも、5分だけでも勉強しておきましょう。
毎日勉強するのが当たり前という習慣化が重要です。
5分じゃ意味ないのでは?と思われる方もいますが、そんなことはありません。
継続して実行すると保護者の方にも意味を理解してもらえることが多いです。
勉強習慣がつかないまま、中学2,3年生になったお子さんで、
土日は極力勉強したくない、というお子さんは意外といます。
そうならないためにも、1年生のうちから対策をしておきましょう。
2年生では本人に目標があるかで変わる
早い子は中2で将来なりたいものや、入りたい高校、場合によっては大学も決まります。
目標が明確であれば、そこから逆算して勉強時間や勉強量を決めていきましょう。
家庭教師などがいれば、生徒と相談しながら勉強のペースを決めていってくれるはずです。
目標がないときは1日1時間
1年生のときに勉強習慣がついていれば、毎日1時間を継続できるようにしましょう。
それと同時に、理解の4段階などをつかって、内容にさらなるこだわりをもちましょう。
1年生の前半は勉強内容が簡単ですが、徐々に難しくなり、1年生の3学期くらいからつまずく生徒が増えていきます。
中学2年生にもなると、英数を中心に、そもそも勉強についていけず、勉強内容がわからないせいで、勉強がしたくなくなる生徒も増えます。
逆に、勉強が全般的に得意な生徒や、特定の科目だけでも得意な場合には、早めに中学3年、高校1年の勉強をすることも有効です。
勉強量ではなく、勉強の質や学校のペースとのズレが問題なので、「勉強しなさい」という保護者の声自体が間違っていることになります。
いままで勉強習慣がついていたのに、勉強量が減った場合は、
勉強以外のことが充実している可能性以外に、
勉強が理解できているのかどうかを確認してみましょう。
3年生は勉強量をうまく増やそう
3年生になると、部活や習い事など充実した活動があれば、そちらを今まで以上に優先したくなります。
また、進路を本格的に考えるために、時間がとられることも増えます。
最後の大会が近いから、これが最後の発表会だから。![]()
最後の○○があっても、勉強時間は確保できます。
これは大人になっても同じですね。
高校受験があっても、なくても。
3年生はとくに前半が忙しくなりやすいからこそ、時間を作る、うまくやりくりする練習機会にしましょう。
勉強量にとらわれなくする
高校受験をするのであれば、部活の引退前でも、毎日2時間くらいは必要です。
難関校を受験する、現状より偏差値が高い学校をぜひ目指したい。
そんな場合は、平日で3~4時間くらいは普通にしていますし、土日は6~10時間くらいしていることはよくあります。
もちろん、ご家庭や本人のやる気、努力度合いによって変わってきます。
また、一番大事なのは継続。
いきなり、毎日絶対10時間、といった高すぎる目標は危険です。
実際、偏差値70くらいの生徒の受験生でも、1日10時間勉強することは非常に少ないです。
むしろ、質が高ければ、1日10時間も頑張ることはほぼ不可能です。
受験や内部進学対策。
中学3年生の大変さは、大変だからこそ精神的成長の役に立ちます。
私の生徒には、中学3年生の時点で自分の宿題計画表を作る練習も始めている生徒が多いです。
学校の勉強以外で役立つ学びを得られるいい機会ですし、高校入学後の大学受験でも推薦などで役に立ちます。
保護者の方へ
お子さんを心配するあまり、保護者の方は
- 学校や塾の宿題
- 勉強時間
の2点に注目がいきがちです。
また、塾をサボっていないか?といった点が追加されることもあります。
残念ながら、これらは全く本質的ではなく、表面をみてお子さん自身を上手く見られないことにつながります。
思春期で難しい時期であり、私も保護者の方からご相談をよく受けますが、愛情が深いからこそ、正面からお子さんを見られていないご家庭も見受けられます。
まずはご家庭でしっかり話をし、上手くいかないときはプロのサービスを利用するのも一つの方法でしょう。
お子さんに合った勉強法・勉強時間・予定管理の指導もしてくれる家庭教師は
→ こちら
よくある質問・料金・web(オンライン)指導などは → こちら
他の記事一覧は → こちら