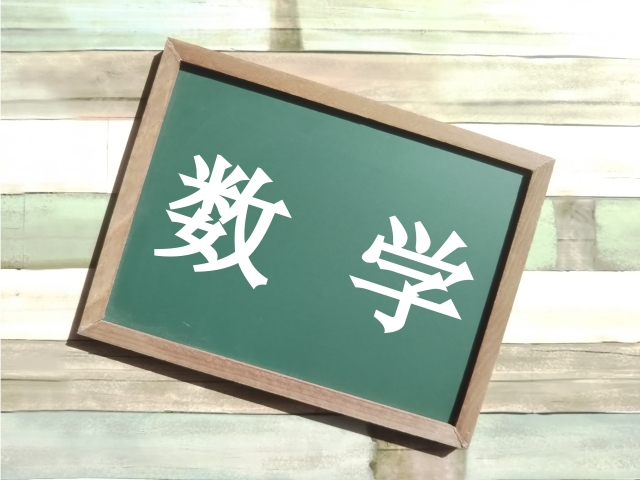経済学部や商学部を受験する場合は数学を選んだ方がいい?
難関大の経済系学部だと、受験に数学は必須・重要なの?
大学受験はいつくらいから受験を見据えて数学を勉強すべき?
文系数学の勉強スケジュール
経済学部や商学部を目指す人にとっての数学
一般的に、経済系の学部は文系理系での分類では文系に入ります。
ご覧の方の中には、高校1年生(生徒およびその保護者)の秋冬で、高校から文系か理系か選択、さらには理科や社会の科目選択でも迷っている人がいるでしょう。
文系の私立大学および大半の国公立大学2次試験の入試科目は、英語・国語・社会の3科目orそこから2科目であることがほとんど。
(総合型などの推薦では小論文や面接が受験科目になることも多い)
ただし、経済系の学部は文系の中でも数学が重要な学部となります。
受験という面で考えても、文系でありながら
経済学部
商学部
経営学部
などは、一部の私立大学は数学が必須もしくは重要な科目として設定されています。
早慶上理ICUおよび関関同立における経済系学部の数学受験
国立大学は基本的に文系でも理系でも共通テストが必須。
数学も必須になるので、2次試験に数学がなくても共通テストで数学が必要となります。
私立大学は大半の学校は数学もしくは社会の選択。
ただし、難易度が高いトップレベルの大学では、数学は「必須」もしくは「選択肢の一つではありつつも数学を選んだ方が有利」な形式として用意されていることも多いです。
以下には関東の難関私立大学である早慶上理ICUと関西の難関私立大学である関関同立における経済・商・経営・政策系の学部での、受験における数学の重要性を大学別でまとめています。
関東(東京)の難関私立大学
早慶東京理科では基本的に数学が非常に重要であり、数学なしの受験はおすすめできません。
本分析には記載がありませんが、MARCHでも経済系の学部を選ぶ場合は数学の方がおすすめになるケースがありますが、社会が得意であれば社会を優先した方がいい大学もあります。
実際には志望校や数学に対する得意不得意、受験までの残り時間で変わってきます。
選択に迷っている場合は、面談などプロにご相談ください。
お問い合わせは → こちら
慶應義塾大学
数学なしでも受験できますが、数学を使えた方が圧倒的に有利です。
商学部
数学必須のA方式は定員が480名に対して、
数学の代わりに社会で受験できるB方式は定員が120名
経済学部
数学必須のA方式は定員が400名に対して、
数学の代わりに社会で受験できるB方式は定員が200名
総合政策学部
4つの選択肢「英語」「数学」「英語と数学」「情報と数学」 数学を避けるには英語のみの選択肢しかありません。
これは環境情報学部も同じです。
早稲田大学
2021年度から政治経済学部で、共通テストの数学が必須となったことがニュースにもなりました。
早稲田大学 → 理工系学部
商学部
数学を使う方式が一定割合あります。
一般、地歴・公民型 数学なし 390人
一般、数学型 数学は独自試験 150人
どちらも同日の試験であり社会と数学も同一時間帯なので併願受験は不可能
政治経済学部
数学必須。
一般選抜は共通テスト+独自試験(総合問題)であり、共通テストの数学が必須。 定員は学部全体で300人。
共通テスト利用も共通テストの数学が必須。
定員は学部全体で50人。
上智大学
経済学部経済学科は数学必須の方式があります。
経営学科は数学と社会or英語の選択
TEAP利用
経済学科
数学必須 文系数学利用30名、理系数学利用10名
経営学科
数学選択 文系数学or社会の選択
学部学科試験・共通テスト併用
経済学科
共通テストの数学と独自試験の数学の両方が必須 85名
経営学科
共通テストは数学or社会の選択 大学独自試験は英語もしくは数学から1つ選択 85名
東京理科大学
経営学部
一般選抜B方式は独自試験の数学必須 (A方式は共通テスト利用であり、A方式でも共通テストの数学は必須)
国際基督教大学(ICU)
一般的な文系の生徒が利用する「人文・社会科学」を受験科目として選択する場合には数学は不要。
総合教養「ATLAS」も高校レベルの高度な数学は受験としては必要ないといえる。
ICUはいわゆる学部という考えはありません。
代わりに31のメジャー(専攻する分野であり、学部というよりも学科やコースに近いイメージ)から選択しますが、その31のメジャーには「経済学」「経営学」「公共政策」などが含まれています。
ICUはアドミッションポリシー(求める学生の資質)として、「文系・理系にとらわれない広い領域への知的好奇心と創造力」を4条件の第一にあげています。
関関同立
関西の難関私立大学である関関同立では、一部をのぞいて基本的に数学か社会のどちらかを選択します。
関関同立分析
関西大学
経済学部・商学部・政策創造学部
どの学部も数学もしくは社会の選択 文系数学分析
関西学院大学
経済学部・商学部・総合政策学部
全学部日程、学部個別日程では数学と社会の選択
英数日程では数学必須 文系数学分析
共通テストでは数学必須と数学選択の両方の形式がある
同志社大学
経済学部・商学部・政策学部
どの学部も数学もしくは社会の選択
立命館大学
経済学部
最大定員の全学統一方式(文系)は数学と社会の選択
経済学科経済専攻
学部個別配点方式(文系型)があり、これは数学必須
共通テストを使う形式は数学と社会の選択
経営学部
どの方式でも基本的に数学と社会の選択
一部方式は英語と国語(と情報)で受験できるので、数学も社会も不要
政策科学部
どの方式でも基本的に数学と社会の選択
一部方式は英語と国語で受験できるので、数学も社会も不要
産業社会学部
いつから受験を見据えて数学を勉強すべき?
結論から記載すると、1年半前が一つの基準です。
ただし、生徒ごとに目指すレベルや数学の必要性、現在の学力やこれまでの勉強方法の正しさが異なります。
私も過去の生徒で早慶のための文系数学や、学校の定期テストや推薦(総合型や指定校推薦など)のための文系数学を指導してきました。
実際には受験の半年前でも十分間に合う生徒もいれば、高校1年生からコツコツ積み上げなければ合格が難しい生徒もいます。
基本的に早くて困ることはない
大学受験に関わらず、大抵のことは早くから準備をした方が有利です。
ただ、現実問題として、小学生のときから大学受験を考えて勉強しているご家庭は非常に少ないでしょう。
(一部のご家庭ではありますが、途中で方針が変わることもよくありますし、小さい時から詰め込みすぎると破綻したり、お子さんが青春を犠牲にしてしまうこともよくあります)
文系数学においては、中学3年生や高校1年生から少しずつ数学も他の科目も対策しつつ、志望校(志望学部)が決まった時点で数学をどうするか決める場合も少なくありません。
数学は積み上げ要素が強いので、点数を上げるのに一定の時間がかかる
例えば文系数学の受験で出題率が高い分野の一つに、数Bの数列があります。
数列をそのまま勉強することも必要ですが、数Aの場合の数・確率と合わせた問題が良く出題されます。
また、数Ⅰで勉強する二次方程式に関わる部分もあります。
数列を勉強する前に数Ⅰや数Aを深く理解していれば、数列の勉強は効率的になります。
理解度も高まりやすく、勉強している生徒自身も楽しみやすいでしょう。
短い勉強時間で点数もとりやすいです。
基本的に数Ⅰや数Aは中高一貫校では中学3年生~高校1年生の1学期に学習してしまいます。
このときの理解が十分であれば問題なく数Bの勉強ができますが、この時の理解が不十分な生徒は高校1年生の夏休みや秋冬を使って復習をしておきたいでしょう。
一般的にはこの復習は受験勉強の一環といえます。
普段の勉強において質が高く理解度も十分であれば、特別受験を意識する必要はありません。
普段の勉強の質が低ければ、結局復習を多くの範囲ですることになるので、受験を考えた勉強を早いタイミングでスタートさせた方が圧倒的に有利となります。
文系数学の勉強スケジュール
実は、文系数学のスケジュールにおいて最も危険なのは中高一貫校に通っていて、数学が得意とは感じていないパターンです。
中高一貫校の数学はペースが早すぎて、結局理解の質が低い生徒が続出している
中高一貫校では一般的な高校と比較して、約1年数学のスピードが早いという傾向があります。
多くの保護者の方が早いから中高一貫校が有利だと考えます。
これは半分正解で半分間違いです。
学校の授業についていきつつ、正しい勉強を継続できている生徒の場合は非常に有利。
実際は大半の生徒が授業のペースについていけておらず、習った分野でも理解が不十分で終わって定着していない。
定着していないから結局最初からゆっくり復習をしなければいけない。
という場合が非常に多いです。
これは恐ろしく非効率。
本当は授業のペースにある程度合わせつつ、一定の時間をかけて理解をすべきですし、それが効率もよく、最終的な合格率も高めてくれます。
中高一貫校で、公式を暗記させられていたり、学校のテストで点数を取れていなかったり、模試になると点数がわかりやすく下がる生徒は黄色信号です。
今すぐ改善方法を考えることをおすすめします。
経済学部や商学部などで数学受験するなら、遅くとも2年生の夏までにしっかり復習したい
勉強スケジュールで重要なのは、基礎の復習ペースです。
基本的にMARCHや中堅国立以上が目標であれば、ⅠAの復習をしっかりしておく必要があります。
高校3年生になると英語などの他の科目や、数学も受験レベルに近い問題が増えます。
そのために、高校2年生の夏休みが終わるまでには、ⅠAの基礎を完璧に近づけておきましょう。
理想をいえば高校1年生のときからコツコツ復習することですが、現実的には1年生の冬か春休みくらいからⅠAの復習をスタートさせましょう。
遅くとも2年生のゴールデンウィークには始めておきたいです。
1年生の冬、もしくは、2年生の春。
これが難関大の経済系学部を狙うためのチェックポイントとなるでしょう。
英語や国語、場合によっては社会とのバランスも考える必要がある
多くの私立大学の受験であれば、英語と国語は文系でほぼ必須。
今回は私立大学の文系受験を考えており、数学を受験科目にしそうな場合を想定しています。
文系で数学を受験に利用するのであれば、前述したように難関校を受験される可能性が高いと思われます。
その場合、そもそも英単語などの英語の基本的能力を高校1年生の間に高めておくことが重要です。
数学を受験科目にするかしないかに関わらず、文系受験の基礎は1年生から無理のない範囲で頑張っておきましょう。
国公立を視野に入れている・第一志望としている生徒は共通テストの科目が非常に多くなるので、ここでは省略します。
国公立受験においてのスケジュール管理についてお話してみたいご家庭は、お問い合わせください。
文系受験の科目で、社会ではなく数学で受験する場合には暗記要素が大幅に減少します。
英単語・英文法・古文単語や漢文構文などは一定の時間がかかるので、高校1年生から少しずつ取り組んでおきましょう。
数学は何よりも理解を優先し、問題を解くことだけに気を取られないようにしてください。 高校2年生では数学優先がおすすめです。
数学4~5割
英語が3~4割
国語が2割程度
のイメージが効率的な生徒が多いです。
実際には生徒ごとに学力や状況が異なるので、あくまで目安とだけお考え下さい。
高校3年生では個人差および志望校差が大きくなるので一人一人バランスが異なるでしょう。
文系数学と合わせて英語なども指導してくれるプロ家庭教師の指導に興味がある方は → こちら
他の記事一覧は → こちら