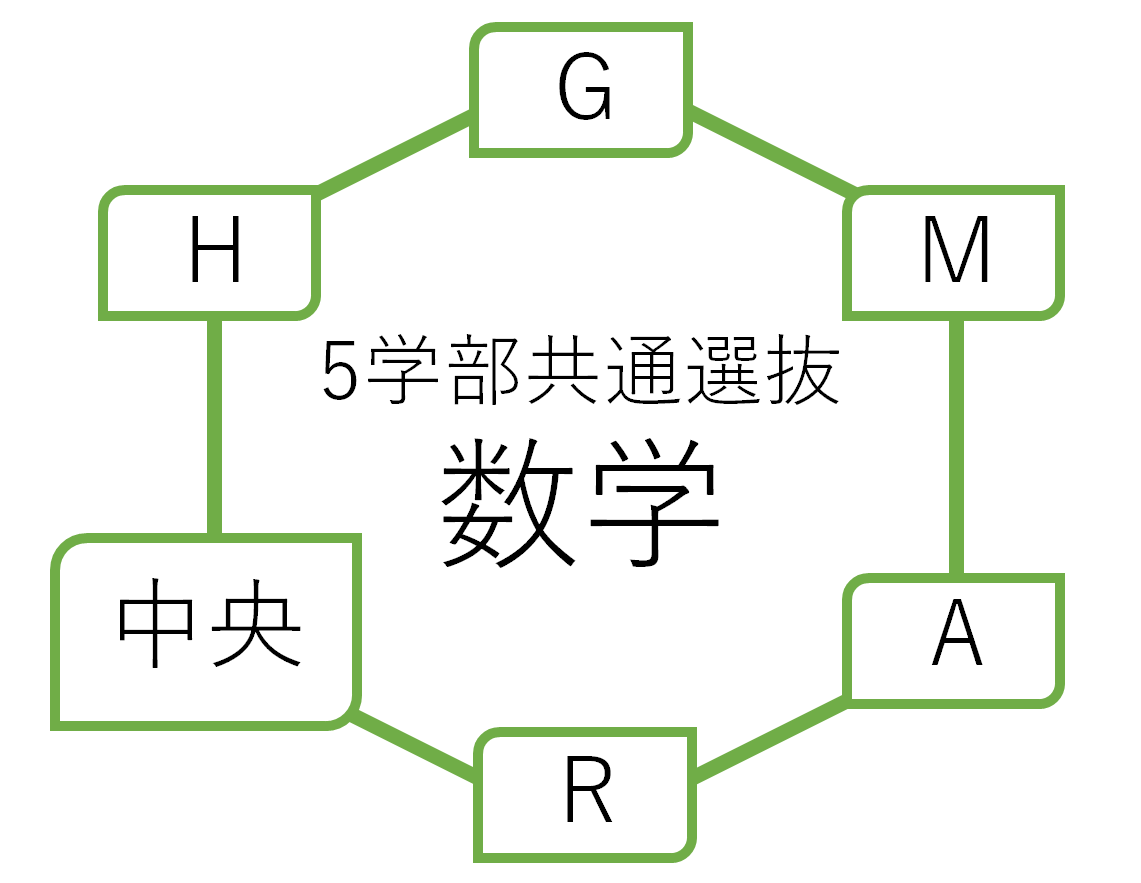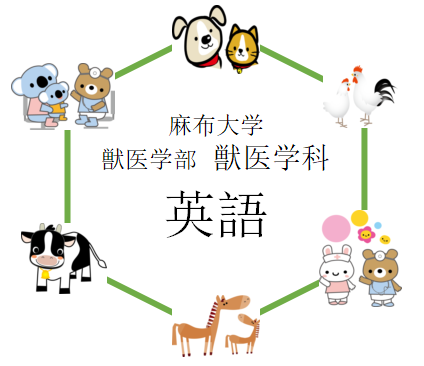中央大学 5学部共通選抜の数学
中央大学では2021年まで統一入試と呼ばれていた方式が、
6学部共通選抜に名前が変更されました。
さらに、2025年の1月以降の入試は5学部共通選抜となります。
時間は60分で、全編記述式でしたが、2022年2月からマーク式に変わりました。
2022、2023年はマーク式でしたが、2025年から5学部共通となるので、記述式が部分的に導入されるなどの変更もあり得ます。
どちらにも対応できるようにしておきましょう。
出題範囲は数学ⅠAⅡBC(数列・ベクトル)です。
中央大学分析 → 5学部共通(英語 日本史) 経済学部 理工学部 法学部
他のGMARCH分析 → 明治大学 学習院大学 立教大学 法政大学
5学部共通選抜が利用できる学部
- 法学部(4教科型・3教科型)
- 経済学部
- 商学部
- 文学部
- 総合政策学部
国際経営学部(4教科型・3教科型)は共通選抜がなくなり、学部別選抜と小論文などがある総合型がメインとなっていきます。
数学の重要度
【数学が必須の学部】
法学部(4教科型)
『数学が選択の学部』
法学部(3教科型)
経済学部
商学部
文学部
総合政策学部
対面授業もオンライン授業も、プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら
全記事一覧は → こちら
変わる部分と変わらない部分に注意
中央大学の5学部共通は表面的な変化が大きくありました。
また、2025年からの指導要領の変化で、表面的に変わる部分や過去に戻る部分も出てくるでしょう。
ただし、本質的な部分や中央大学が求めている質の高い生徒の条件は基本的に変化していません。
共通テストではなく、旧センター試験のような問題へ
もともと2021年2月の共通選抜まで、数学は完全記述式でした。
2022年からマーク式。
分数や桁数までわかる、共通テストやセンター試験と同じようなタイプのマークとなります。
共通テストは難易度設定や出題傾向が合わないと感じている大学が多く、見直しが増えています。
そして、評価が高かったセンター試験に近い傾向が、現在の中央大学の数学となっています。
本質的理解と計算力
しっかりした理解と、正しい蓄積が求められています。
また、時間内に一定量の問題を解かなければいけないので、そこそこの速度は求められます。
ただし、今の共通テストや旧センター試験のようなかつかつになるほどの速度は不要。
合格のためには正確性の方が圧倒的に重要になっています。
出題傾向は王道に戻る
2021年までは、出題範囲は他の大学と違う部分も見られました。
しかし、ここ数年は戻ってきており、どの大学でも重要視されている分野からの出題率が高まっています。
ここ数年は、
大問1は数Ⅰと数Ⅱ
から出題。
大問2,3,4は、
数BとC(数列とベクトル)
数A(場合の数・確率)
数Ⅱの微分積分
が定番となっています。
各大問の流れも自然
それぞれの分野をみても、入試問題として自然かつ標準的な流れで出題されています。
簡単ではありませんが、これまでと難易度が大きく変わっているわけではありません。
特に、合格最低点である60~70%を考えると、難しい問題をどんどん解けるような学力は不要です。
公式暗記が無効ではありませんが、一定量まで理解を目指す正しい勉強方法を継続することが重要です。
理解の上に典型パターンを乗せれば合格最低点を超えることはそこまで難しくありません。
まとめ
保護者の方へ
中央大学の数学は、難しいですが対策はしやすいです。
過去の傾向も現在の傾向も、求められている学力は同じ。
高校1年生の時から正しい勉強を積み重ねていれば、高校の偏差値が40~50くらいの文系の生徒でも十分に合格点が取れます。
逆に怖いのが勉強方法を間違えている自信家な高校2年生や、失敗の原因が分かったと豪語している浪人生です。
ぜひ、質の高い積み重ねを継続できる環境や先生を用意してあげてください。
偏差値40からGMARCH合格を目指すなら → こちら
他の記事一覧は → こちら