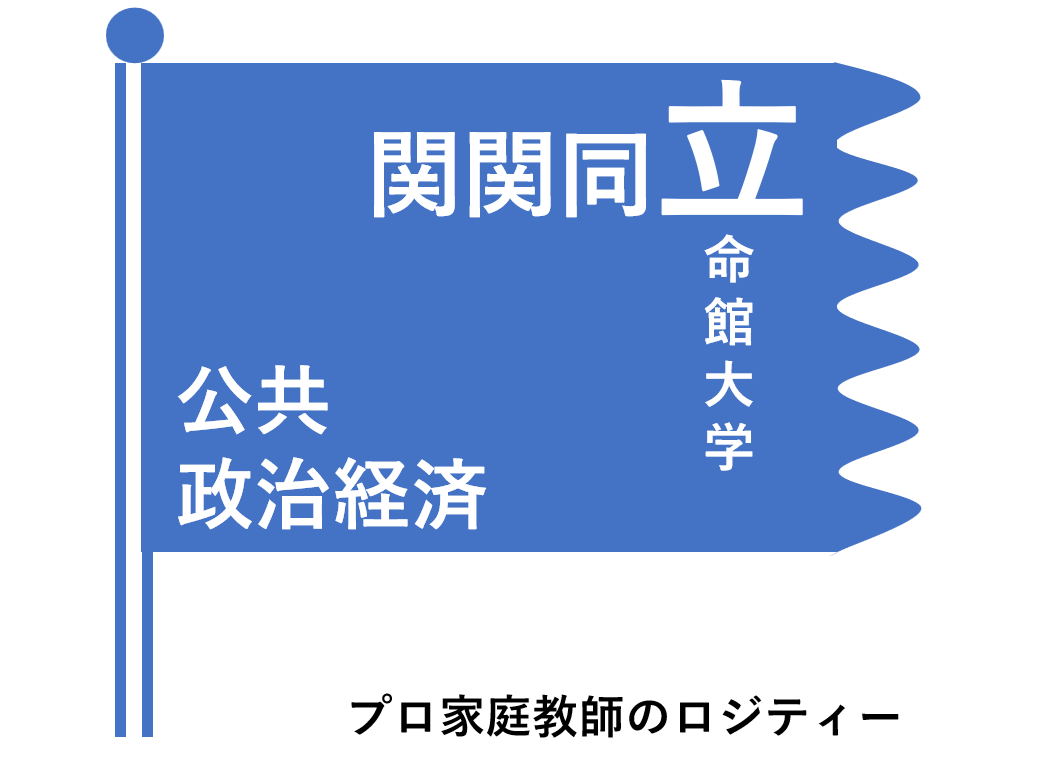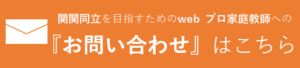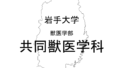立命館大学での政治経済
立命館大学には、複数の試験方式がありますが、メインとなる方式は
全学統一方式
学部個別配点方式
があります。
今回は全学統一方式の文系学部の過去問がメインですが、学部別配点方式の政治経済も傾向は近いです。
両方に使える分析となっています。
公民なら政治経済
立命館大学における社会は
地理(地理総合・地理探求)
歴史(日本史探究・世界史探究 :歴史総合は含まれない)
公民(公共・政治経済)
が主にあります。
公民は大学や学部によって選べる科目が制限され、立命館大学では政治経済のみ。
立命館大学では公共・倫理は選択できず、多くの大学で同様の傾向です。
ただし、共通テスト併用などでは政治経済以外の公民科目も選択肢に入っています。
基本的に公民が選べる学科で選択肢にもっとも入りやすいのが政治経済。
他の大学以外での選択肢や、難易度や内容理解のしやすさ、他の科目との暗記のバランスを考えても、選ぶなら政治経済一択といえるでしょう。
倫理は高校レベルでは単純暗記比率が高くなってしまうので、学ぶ楽しさという面でも政経がおすすめです。
全学統一方式で政治経済がある学部
法学部
産業社会学部
国際関係学部
文学部
映像学部
経営学部
政策科学部
総合心理学部
経済学部
スポーツ健康科学部
食マネジメント学部
学部個別配点方式で政治経済がある学部
法学部
産業社会学部
国際関係学部
文学部
映像学部
経営学部
政策科学部
総合心理学部
経済学部
スポーツ健康科学部
食マネジメント学部
立命館大学分析 → 日本史 理系数学 化学 生物 生命科学部 薬学部
政治も経済もバランスよく出題
立命館大学では3つの大問構成。
他の大学では経済が多めに出題される大学もありますが、立命館大学では出題に偏りが少ないです。
政治分野も経済分野も国際分野もまんべんなく出題されやすくなっています。
用語は書けるように覚える
各大問では問題の長文中に空欄があり、用語を記載しなければいけません。
私立大で選択式のみの入試も少なくありませんが、政治経済では用語は書かせる大学が多めになっています。
また、経済学部、商学部、経営学部などでは長めの記述がある学部別入試もありますが、立命館では文章での記述問題はありません。
用語さえしっかり書けてしまえば暗記としては十分といえます。
よくある質問・料金などは → こちら
web授業に関しては → こちら
公共用語も忘れずに
公共には倫理の要素も含まれており、政治経済で使われる用語と毛色が異なります。
政治経済の用語はニュースサイトや親子の会話などで経済に触れている生徒には身近ですが、倫理にかかわる用語は覚えにくい生徒も少なくありません。
重要度は当然政治経済の用語ですが、一つの科目の中でも自分なりに差をつけて、時間に余裕があれば公共の用語も書けるようにしておきましょう。
優先順位のアイディアが必須です。
難易度は標準的
問われる知識としてところどころに細かいものがないわけではありませんが、総じて標準レベルといえるでしょう。
勉強過程で理解は必要ですが、問題の中で高い思考力を求められる部分はなく、正しい勉強ができていれば高い正解率を出すのは難しくありません。
歴史的要素や国際問題も重要
国際政治や条約、為替といった世界に目を向けた問題も当然出題されます。
他の大学では国際関係の大問をほぼ100%出題するところもありますが、立命館では出題比率は高いものの100%とまではいきません。
重要なのは変わりないので、国際系は国際法も含めてしっかりおさえておきましょう。
時事用語はないが、話題の項目は理解しておくべき
ここ数年は戦争だけでなく為替など世界的ニュースが多くなっています。
入試問題で明確に時事枠があるわけではありませんが、時事項目は勉強のきっかけがつかみやすいので、一定の勉強をしておきましょう。
歴史と流れが大切
関連法令が制定された順番が聞かれる問題もあり、政経でありながら過去の時代背景を理解していると有利になります。
1つ1つの出来事を単独で覚えると不利になり、流れを理解している必要があります。
1900年代の後半に関する政治・経済の事項は高確率で出題されているので、日本史や世界史の現代史(歴史総合にも含まれる)の部分は、政治経済で一定の勉強をしておきましょう。
参考書・問題集
暗記しやすさではなく、理解しやすさで参考書を選びましょう。
公共・政治経済は社会科でも理解の重要性が高く、世間の評判よりも自分が勉強しやすい参考書がよいでしょう。
本屋さんで迷ったときは政治・経済が面白いほどわかる本(Amazonリンク)や共通テスト 集中講義(Amazonリンク)などに目を通してみるとよいでしょう。
シグマベストの理解しやすい政治経済(Amazonリンク)もおすすめです。
理解という面で考えると、教科書はおすすめできません。
問題集
問題集は、最初は知識の確認があり、中盤以降では経済分野を中心に理解と暗記の両方が確認できるものが最適です。
一問一答タイプの問題集(Amazonリンク)は悪くはありませんが、一問一答だけでは確実に不足がうまれるので注意してください。
また、長い記述は不要ですが、単語の記述を多く求める問題集であることも重要です。
まとめ
- 政治経済は選択科目としておすすめ
- 時事ネタは無理なく追いかける
- 国際の重要性も忘れずに
保護者の方へ
立命館大学は関西でハイレベルな大学ですが、政治経済はそこまで難しくありません。
偏差値55~60くらいの思考力、理解力があって、暗記が苦手でなければ、1年間しっかり勉強すれば十分に入試対策として合格を目指すことができます。
お子さんが
文系選択者で英語や国語などに時間を使いたい
急に文系に進路を変更した
といった場合にも、政治経済は選びたい科目といえるでしょう。
ただし、現在の英語・国語、社会の3科目総合偏差値が50を下回っている場合には、受験勉強1年では合格が難しくなります。
お子さんの現状に合わせて勉強方法を変更しつつ、受験対策はできれば1年半~2年前から。
部活なども頑張りつつ、高校2年生から少しずつ積み重ねましょう。
プロ家庭教師の指導に興味がある方は → こちら
他の記事一覧は → こちら