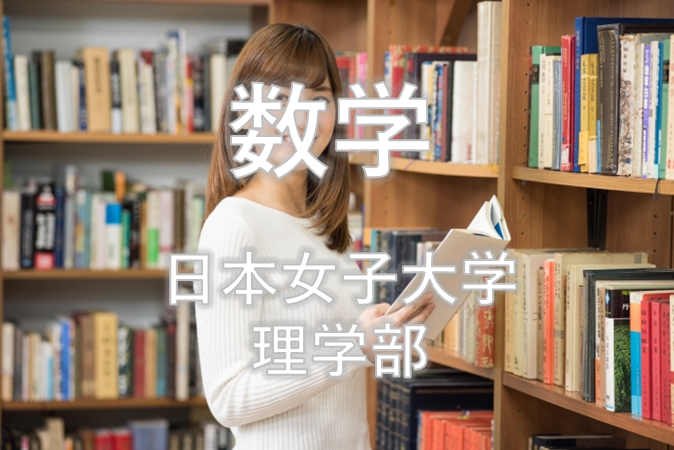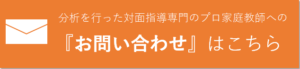日本女子大の数学
数学は数物科学科では必須。
物質生物科学科では、理科を選択すれば数学は選択しなくても大丈夫になっています。
大学で数学や物理、情報を勉強するのであれば、高校レベルの数学は必須です。
時間は70分で100点満点。
記述式ですが、証明は基本的に出題されず、最終的な解答には具体的な数値が出てきます。
大問が4つに対して、90分は一般的な時間設定ですが、各大問では計算量が比較的少なめなので、時間には余裕があります。
ある程度時間をかけてでも正しい解法の流れを導き出し、丁寧に頑張れる生徒を求めていることがわかります。
拙速よりも巧遅が優先されます。
日本女子大学理学部の分析 → 基本情報 英語分析 化学分析 生物分析
他大学の理学系学部分析 → 学習院大学 中央大学 法政大学 他の大学分析
女子大分析 → 東京女子大 津田塾大 実践女子大 昭和女子大
2025年1月以降(新課程)の入試に関して
現時点で高校1,2年生および浪人生が対象となります。
教育指導要領変更後の2次試験 2023年4月から新しく高校2年生になる学年は、テスト範囲(主に数学)が変わります。
以下は現在高校1,2年生および現在高校3年だけど浪人しそうな生徒用となります。
理学部の数学は、
ⅠA(Aは図形の性質・場合の数と確率)
ⅡB(Bは数列)
ⅢC(Cはベクトル・平面上の曲線と複素数平面)
となります。
これは2科目型でも3科目型でも同様です。
範囲は全般・難度は標準
理学部の数学ということもあり、範囲はⅠAⅡBⅢ。
入試には必ず数Ⅲの範囲が出題され、中心となりますが、ⅠAⅡBからも十分な出題量があります。
![]()
出題範囲はしぼりやすい
数Ⅲでは微積が中心ですが、極限や複素数平面の問題も出題されます。
微積以外の範囲は基礎的要素が強いので、微積を重視し、それ以外の範囲は基礎を重視しましょう。
ⅠAⅡBでは、
- Aの確率
- Ⅱの三角関数
- Bのベクトルと数列
これらの範囲は特に頻出です。
もちろん他の範囲も出題されますが、出題頻度としては上記が明らかに高いので、勉強する順番を工夫しましょう。
難易度
難易度としては典型的な問題が多く、定期テストで最も難しい問題や、学校で使われる問題集の難しめのレベルとなっています。
一般的な問題集では黄色チャートレベルが中心です。
ひねった問題や定理の根本的理解を問う問題は少なく、典型的で確実におさえておきべき問題が中心。
GMARCHレベルの理学部よりも1~2ランクほど取り組みやすいですが、決して簡単ではありません。
Ⅲは対策しやすい
数Ⅲが一つの障害となりますが、難易度自体は高くありません。
また、典型的な問題のみで、微積からの出題頻度が高いので、勉強がしやすくなっています。
数Ⅲがあるから日本女子をあきらめる、というのはもったいないでしょう。
対策・勉強法
理学部の数学では根本理解をより求めた応用問題と、基本に忠実に典型的なパターンを正確に解ける標準問題のどちらかが多いですが、日本女子大は後者。
真面目に典型問題のパターンを多くおさえておくことで、合格点を取りやすくなっています。
勉強方法として、理想をいえば各定理の根本理解ですが、合格点を取るだけであれば数Ⅲの微積を中心に、パターン暗記を中心に行うことです。
問題集は標準レベル
黄色チャートなど、難しすぎずに典型的なパターンを網羅できる問題集が最適です。
実際の問題にはときどきこれらの問題集を超えるケースがありますが、少ないです。
最初から難しい問題集で演習スピードが落ちてしまうと、時間切れになり、最重要な数Ⅲの演習が不足しやすくなります。
数学によっぽど自信があれば、青チャートレベルでも構いません
黄チャートや学校で使っている問題集をベースにすることをおすすめします。
計算量より解法を身に着ける
数学の基本はもちろん計算です。
大問1は小問集合となっており、旧センター試験のような計算練習が特に合います。
日本女子大の数学は計算量は少ないですが、最低限の計算力がないと当然合格できません。
入試の計算量が少なくても、問題集の各章での序盤にある計算問題は最低2回転は行い、まずは基礎計算力を高めましょう。
共通テストレベルやセンター過去問題で基礎力を高めよう
共通テストレベルで70点程度は毎回取れる計算力は必須です。
ただし、日本女子大対策として共通テストの勉強は不適。
特にⅠAは完全に内容が異なります。
少し古いですが、センター試験の過去問や問題集がおすすめです。
根本理解が難しければ、解法暗記も一つの解決法
計算力がついたら、解法を身に着ける練習です。
根本理解が理想ですが、なかなか理解が難しい問題は、解法を覚えてしまいましょう。
最初に解法の流れをしっかり読んで可能な限り理解し、不明な部分は理解がなくても何度も書き写してみましょう。
さらに、問題を見て、解答の流れを想像する練習も効果的です。
頭の中で解法が思いつかない場合は、きちんと書いてできる計算をしっかり行って自力でできるかチャレンジしましょう。
まとめ
- 全般の基礎が身についたら重点分野(微積や確率など)を練習しよう
- 計算力をつけたら解法力を育てよう
- 難しすぎる問題は不要
偏差値を大きく上げて理学部合格を目指すなら → こちら
他の記事一覧は → こちら