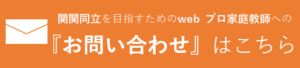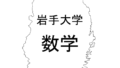立命館大学の日本史
立命館大学には、複数の試験方式がありますが、メインとなる方式は
全学統一方式
学部個別配点方式
の2つがあります。
この2つの方式はどちらも立命館大学の独自試験として地理歴史公民(政治経済)があります。
当然日本史の独自試験もあります。
2025年2月に行われる新課程での入試では、日本史探究のみとなり歴史総合は入りません。
地理歴史は世界史も歴史総合なしの世界史探究のみですが、地理は地理総合と地理探究の両方が範囲なので注意してください。
立命館大学分析 → 理系数学 化学 生物 生命科学部 薬学部
共通テストの範囲に注意
共通テスト方式では、基本的に社会は選択科目として1つ選ぶ可能性が高いです。
範囲は歴史総合・日本史探究。
全学部で選択可能です。
歴史総合を学ぶかどうかは、国公立を視野に入れるかどうかだけでなく、私立の併願校も考えならばえらぶとよいでしょう。
2024年度(入試日は2025年1~3月)において、私立の一般入試(大学ごとの独自試験)でも歴史総合が必要な大学と、不要な大学に分かれています。
同志社大学や近畿大学は、立命館同様に歴史総合が不要です。
一方で関西学院大学は歴史総合が必要となります。
関西の関関同立や産近甲龍でも差があるように、関東のGMARCHでも大学ごとに違いがあります。
時には同じ大学内でも学部や学科で範囲が違うこともあるので、しっかり確認しましょう。
3つの大問はそれぞれの時代から
大問は3つ
大問1が原始・古代
大問2が中世・近世
大問3が近代・現代
となっています。
ただし、大問3は大問1,2にくらべて若干問題数が多い年が基本。
配点は明記してありませんが、大問3が少し高めとなっているでしょう。
近現代はどの大学でも重要視されやすいので、立命館対策としても併願校対策としてもしっかり頑張りましょう。
原始・古代の対策は難しい
日本史において時代が古いほど出来事や人の関連性が薄くなり、単純暗記比率が高まります。
立命館ではこの時代で基礎~標準レベルだけでなくそこそこ覚えにくい難易度高めの問題も多少出題されています。
どこまで覚えきって、どこまでは無理しないかのライン設定は難しいですが、古代は学校で学んでから復習の感覚が長くなりやすく、勉強方法で差がつきやすいです。
ただがむしゃらに覚えるのではなく、勉強計画も含めた工夫が必須となります。
現在の高校1年生は歴史総合を勉強中で、昔の時代を本格的にはじめるのは高校2年生の最初が多いでしょう。
これから2年間で勉強する流れを理解しておくと、精度が高まり効率的になります。
用語記載は当たり前
立命館の日本史は選択式と単語記載の併用。
文の記述はありません。
メインが単語記載なので、各単語の漢字を正確に記載できることは前提条件。
男の子に多いですが、字が読みにくく正確な判定がしにくい生徒は注意してください。
美しい字を書く必要性はありませんが、採点者が判別できる字にしないと、バツになる可能性が高いです。
地図の重要性は高くないけど多少ある
全体を通して地図や地理的要因が関連した出題は少数。
地図が実際の問題用紙に一つも記載せれていない年も多く、現状日本史探究のみで歴史総合が出題されない範囲を考えると、地図の重要性は低いといえます。
一方で、現在の高校1年生や2年生は地図が必須。
出来れば中学時代の社会を勉強する時点で一定程度の理解をしておきましょう。
新課程になった年は移行期間として浪人生への配慮が行われますが、今後は歴史総合もテスト範囲に入る可能性は十分にあります。
歴史総合をみすえて、日本史と世界史の地理的なつながりに慣れておく方が絶対的に有利です。
受験勉強という意味でもそうですが、大学生・社会人として最低限の地理が理解できていないことはありえません。
特に立命館レベルを卒業している生徒なら本当にありえないので、今のうちに受験勉強もかねて用意しておきましょう。
難易度は平均的にプラス
全体的な難易度としては標準レベルが5~7割くらい。
共通テストや一般的な大学入試レベルの問題集・参考書を網羅していれば、合格点を確実にとることができる難易度となっています。
一方で、なかなか細かい暗記が求められる部分も一定数みられます。
全体として一つの時代にフォーカスするよりも、時代を広くとらえて様々な年代から出題されます。
年によっては一つの大問を2~3つに分割して出されることもあります。
歴史は本来流れが重要ですが、立命館はどちらかというと理解より暗記に偏っており、真面目にコツコツ積み上げる必要性が高いです。
難易度も理解よりも知識で上げてきているので、勉強方法には注意が必要です。
単純暗記も限界があるので、一人一人にあった暗記と理解のバランスを探りながら勉強しましょう。
よくある質問・料金などは → こちら
web授業に関しては → こちら
文化史も勉強必須だが、比率は高くない
文化史は出題自体はありますが、全体的には少数といえます。
文化史よりも縦の糸を中心とした時代の流れの日本史を中心に勉強しましょう。
勉強しなくてもいい、とまでは言いませんが、残された時間と得意分野を考えて、文化史の優先度は下げてもよいでしょう。
図も少ない
立命館では地図と同様に、図や史料が示されることもあります。
ただし、全体を通して0~2問程度と図に絡めた問題の比率は低いです。
文化史に関わる出題はもう少し多いですが、絵や建築、石器など図を通して文化史に関わる出題につなげる問題は少数といえるでしょう。
文化史も平均レベルの用語を大切に
一般的な日本史の出題にありがちな用語および選択肢として文化史も長文中から出題。
使われている・問われている用語も標準レベルが中心。
学校の定期テストを細かく勉強していれば一度は見たことがある様な用語が多く、立命館のために特別に文化史を頑張る必要性は低いといえます。
ただし、継続的な積み重ねが必要であり、文化史の勉強時間を残すためにも、遅くても高校2年生の夏~秋には歴史の受験対策にのりだしましょう。
参考書・問題集
標準的な用語が網羅されており、流れもあるていど理解しやすい参考書がおすすめです。
山川の教科書(Amazonリンク)は王道であり、細かい部分も含めて暗記ができますが、少し細かすぎるとも言えますし、流れの理解はしにくいです。
細かすぎる知識がありすぎると勉強がしにくい生徒は、実況中継(Amazonリンク) などが使いやすいでしょう。
分厚くても大丈夫であればMYBESTのよくわかる高校日本史探究(Amazonリンク) もおすすめです。
また、文化史は出題比率が高くないので、文化史が別冊になっている参考書も有効でしょう。
メインの流れを重視して、余裕があれば文化史の参考書も使うと勉強しやすいです。
問題集
難易度と出題に特殊な部分は少なく、一般的かつ標準的な知識を確認できる問題集がいいでしょう。
教科書は配布してくれますが、日本史は問題集がない、あっても一問一答程度という高校が多いです。
共通テスト形式と立命館をはじめとした関関同立対策は異なり、問題集も違うので、自分の勉強方法に合った問題集を選びましょう。
注意してほしいのが、立命館が一問一答の暗記が多いからといって一問一答のみはおすすめできません。
一問一答と流れがある問題集は目的が異なり、使うべきタイミングも生徒によって異なります。
問題集を買う前に、自分にとって効率な勉強スタイルを考え、参考書との相性も考えましょう。
おすすめされたから「これ」を買うという考えない問題集選びはやめた方がいいです。
まとめ
保護者の方へ
立命館大学は難易度が非常に高く、日本史単独で見ても高い知識レベルが必要な問題もあります。
一方で、合格に必要な点数を考えると標準レベルの暗記が重要。
暗記が重要といっても、膨大な日本史を単純暗記ばかりで乗り切ることは非現実的。
大切なのはただ教科書を読み、なんとなく問題集を解くのではなく、正しい歴史の勉強方法・自分の子に合った勉強方法を考え、試してみることです。
勉強を始める前の準備段階が最重要。
お子さんはなかなかそのことに気づかず、目の前のことで精一杯になってしまいます。
保護者の方がお子さんに先んじて塾や家庭教師など、お子さんの勉強方法と長期計画に向き合ってくれる人がいると、かなり有利になるでしょう。
プロ家庭教師の指導に興味がある方は → こちら
他の記事一覧は → こちら