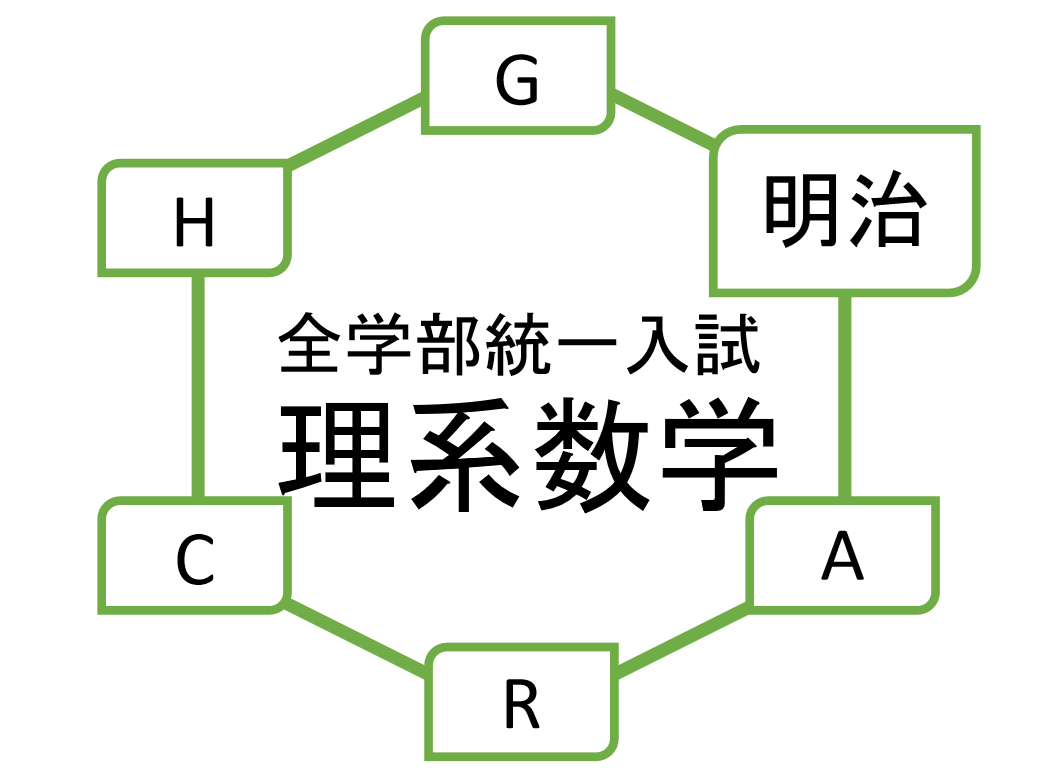明治大学 全学部統一入試の理系数学
明治大学の学力が重要な入試である一般選抜は、
全学部統一入学試験
学部別入学試験
共通テスト利用入学試験
の3種類があります。
中でも全学部統一入学試験は、問題が全学部で共通。
一度の受験で複数学部を併願でき、全国の8都市で受験することが出来ます。
理系数学は主に数Ⅲのみで構成されていますが、全学部統一入試では理系数学(数Ⅲ)の受験者は文系数学(ⅠAⅡBC)も受験しなければいけません。
理系数学(数Ⅲ)が100点
文系数学(ⅠAⅡBC)も100点
合計で200点と数学の配点が非常に大きくなっています。
テスト範囲は、
数学Bが数列、統計的な推測
数学Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面
となります。
ただし、文系数学(明治の全学部統一だと4限に相当する科目)では数Cはベクトルのみとなります。
明治大学分析 → 農学部(英語 文系数学 化学) 全統入試 理工学部 総合数理学部
他のGMARCH分析は → こちら
プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら
理系数学が全学部統一入試で【必須】の学部・学科
理工学部(Amazonリンク)
総合数理学部(4科目)
理系数学が全学部統一入試で『選択』の学部・学科
政治経済学部
全学部統一入試だけでなく、学部別入試でも理系数学があるのは理工学部と総合数理学部のみです。
よくある質問・料金などは → こちら
web授業に関しては → こちら
数Ⅲが4つ並ぶのは本当に高難易度か
多くの受験生にとって難易度が高いとみられる数Ⅲ。
明治の全統では文系数学と理系数学の両方の試験があるので、数Ⅲにどれだけ時間を割くべきか、スケジュール管理が重要となります。
新課程となり、2025年1月以降の入試から数Ⅲの範囲が狭くなりました。
2024年以前は数Ⅲに平面上の曲線と複素数平面が入っており、本分析では平面上の曲線と複素数平面が理系数学で問われる前提で解説していきます。
メインが数Ⅲの微分積分(極限)であることは、これまでもこれからもかわらないでしょう。
小問集合からはじまる
基本的に基礎的な計算問題が2問出題されるのが近年の傾向です。
計算問題ではありますが、数Ⅲの要素がメインで難易度がしっかりとあります。
標準の典型問題が中心です。
大問2以降の難易度を考えると満点を狙いたいところですが、自分の得意分野と時間を調整しながら取り組みましょう。
全範囲の学習が必須
一般的な大学の出題傾向として 数Ⅲの出題頻度が高い範囲は微分積分および極限。
次いで複素数平面(数Cに移行)。
平面上の曲線(旧:式と曲線、数C)は圧倒的に出題頻度が低い
という大学が多いです。
明治の全学部統一は違います。
理系数学はほぼ全部の大問で数Ⅲの要素があり、他の大学で出題されにくい楕円であったり放物線といった平面上の曲線(式と曲線)の出題率が高いです。
基本的に大問が4つあるので、新課程でどうなるかは不明ですが、これまでの傾向からいくと2年に1度くらいは出題されています。
微積などの重要性が下がるわけではなく、まんべんなく全範囲の勉強が必要になります。
勉強時間のコントロールが非常に重要になる
数Ⅲは公立高校では勉強が遅くなりやすく、平面上の曲線(式と曲線)は併願校や明治の学部別日程から優先順位を下げざるをえません。
一方で早くから数Ⅲにとりかかるスケジュールを組んでいる中高一貫校(私立が多い)の有利が出やすくなっています。
微分積分は数ⅢCの中心であり、どの生徒も重要性を理解していますし、勉強時間も長くしやすいです。
その考えは正解です。
ただし、明治も含めた難関校の理系数学は、微積だけで終わらず数Cもしっかり勉強することが必須となります。
中高一貫には落とし穴がある
数学を早く終わらせる学校は、だいたい4~7割くらいの生徒で基礎力が不足しています。
これは、偏差値が高くてもそこまで差がなく、偏差値60~67,8くらいの学校の生徒でも部分的~5つ以上の分野で基礎力の不足がみられることが多いです。
このあたりの偏差値の生徒は明治のをはじめとした大学を第一志望として考えやすく、きっちり復習をしながら学校のペースも考える必要があります。
偏差値70を超えると基礎力が大幅に不足する分野はかなり減りますが、そういう生徒はそもそも明治を第一志望にする可能性が下がっているでしょう。
学校の授業が早すぎて、生徒が正しい理解をできない状態で次の単元に進んでしまうのです。
特に数学ⅠⅡABあたりは基礎力が著しく低いせいで、暗記に頼った数学になっている生徒が多いです。
暗記頼りの数学では明治クラスだと通用しません。
保護者の方は、お子さんを中高一貫にいれて数学に強いと勘違いしがちです。
学校の方針ではなく、模試の判定でもなく、お子さんの状況を見てあげることが必須です。
質の高い先生が直接見れば1~2カ月で基礎力が不足しているのかわかります。
分かりやすい生徒だと1回の授業でわかります。
逆に、公立校だから時間をかけて基礎力が高くなるとはいえず、教科書などを使った間違った勉強になっている生徒も多いので注意してください。
平面上の曲線(式と曲線)と複素数平面の難易度は高くない
明治の全統での上記2分野は、標準レベルからの出題が多いです。
数Cとなった平面上の曲線と複素数平面の重要性が、明治では高いといえます。
基本的な理解をきっちりして、典型問題のみを学習するだけで合格最低点くらいの実力は身につきます。
学校の定期テストなどの進行速度に惑わされず、時間を多めにかけてでも基礎力を身につけましょう。
必ず受験に有利になります。
最後の1つが難しい
全体の流れを見ると、各大問はだいたい3つのパートになっています。
最初は基礎計算もしくは基礎的な理解度を試す問題
中盤が標準的ながら一定量の計算などが入る問題
最後に難易度の高い問題
理解に基づいた正しい勉強が出来ていれば、最初と中盤まではどの大問も解ける可能性が高いです。
最後の難易度が高い問題は、得意分野では積極的に解くべきですが、自信がない大問は飛ばすなど工夫が必要です。
参考書・問題集
全学部統一の理系数学という観点では、黄色チャートレベル(Amazonリンク)がおすすめです。
ただし、学部別入試や併願校まで考えた場合には、青チャート(Amazonリンク)が有効な生徒も多いでしょう。
大切なのは大学のレベルだけを見ないことです。 現在の自分の学力と志望大学とのバランスで決めましょう。
迷ったときには大学レベルより自分のレベルを基準にしましょう。
まとめ
保護者の方へ
明治大学の数学は全学部統一も学部別試験もどちらも高難易度。
特に数Ⅲがメインの全学部統一試験の理系数学は日々の勉強がいかに正しいかを問われ、高校2年から受験を見据えた勉強が必須と言えます。
理解の数学が出来て当然。
勉強方法を早くから正しておけば、理系数学だけでなく文系数学でも高得点が取れるようになるでしょう。
明治クラスの特に理系を中心に考えるのであれば、高校2年の夏には大学受験を考えて準備をしましょう。
なんとなくで塾や家庭教師を選ぶのは危険です。
プロ家庭教師の指導に興味がある方は → こちら
他の記事一覧は → こちら