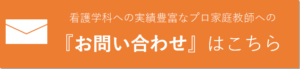慶應義塾大学の看護の数学
慶応義塾大学 看護医療学部(Amazonリンク)の看護学科では、英語は必須科目。
数学は選択科目の一つとなっています。
時間は80分で、配点は200点。
範囲はⅠAⅡBCとなります。
看護学科の数学は、他の大学ではⅠAのみの大学もありますが、看護の中でも偏差値が高い大学はⅡBCも求められます。
数A:図形の性質・場合の数と確率
数B:数列・統計的な推測
数C:ベクトル・平面上の曲線と複素数平面
また、英語、選択科目(数学or理科)に加えて小論文が必須であり、3科目のバランスを考えた勉強をする必要があります。
看護学科分析 → 上智大学 杏林大学 北里大学 その他の大学分析
女子大分析 → 東京女子大 津田塾大 実践女子大 昭和女子大 日本女子大
5つの大問で高い難易度
80分の時間制限で大問5つは普通に考えるとかなり多いです。
ただし、問題をよく見てみると計算が多く、全て答えの数値を穴埋めする形式。
過去には大問5が完全記述式でしたが、現在では記述の大問は一切ありません。
満点に近い点数をとることは難しいですが、合格点をとることは十分に可能になっています。
筆記試験がある1次の合格最低点は500点満点中270~280点とだいたい55%前後。
数学では半分ちょっと取れれば十分といえます。
現実問題として、理科のどちらかを選択する生徒が多いかと思いますが、数学が得意な生徒や暗記が苦手な生徒は数学選択も視野に入れるといいでしょう。
最初の2つの大問は小問集合
最初の大問は4~5問の小問集合です。
どれも基本的で典型的な計算ばかり。
式が1~2つで解答が完成するので、公式をそのまま当てはめる問題になります。
ジャンルは幅広くどこから出題されるか予測できませんが、すべての基礎なので恐れることはありません。
学校の定期テストをしっかり勉強し復習していれば確実に満点を狙うことができます。
逆にここで満点を狙えないのであれば、数学選択は厳しいといえるでしょう。
2つ目の大問も小問集合
2つ目も3~5問程度の小問集合になっています。
こちらも基本的に大問1と同様ですが、少し難易度が上がっています。
1つの小問に対して計算式を2~3つ作って回答する必要があるため、大問1よりも1問あたりに必要な時間が長くなります。
基本的にこの2つの大問でほぼ全範囲を網羅しており、範囲を絞って勉強することができないようになっています。
逆に、1つの分野で大量点を失うこともありません。
この分野だけはどうしても苦手というものがあった場合、戦略的に最初から勉強しないという方法もあります。
苦手分野が少ない生徒は、大問1と2でほぼ満点に近い点数を狙いたいです。
一方で、この2つの大問で8~9割とれていれば、合格が一気に近づくので、この2つの大問に大幅に時間をかける価値があります。
もしも数学で点数を稼ぐのであれば、大問1,2で30分程度しか使えませんが、普通の受験生であれば50~60分かけてかまいません。
丁寧に図を描いたり、計算前に公式を書いて確認することが有効といえますし、検算など計算に時間をかけてでも正確性を高めた方が合格率が上がります。
後半が大問
大問3,4,5はそれぞれ一つの単元に関する大問になっています。
プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら
全記事一覧は → こちら
大問3,4はABCが中心
この2つの大問ではある程度ジャンルを絞ることができます。
それがAとBとC
Aの場合の数と確率、図形の性質
Bは数列
Cはベクトル
これらはどの大学でも比較的出題頻度が高いので、勉強をしておいて損はないです。
大問3が数Ⅰのデータから出題された年もあるので、100%AとBとCから出題されるわけではありません。
2024年も数Ⅰのデータの問題が出題されており、看護学における数学(特に統計学)の重要性を大切にする姿勢がうかがえます。
数Bの統計的な推測と、数Cの平面上の曲線と複素数平面は新課程で文系数学でも必要な可能性が出てきました。
共通テストなどではどちらか選択できるのが基本であり、看護系の数学ではそもそも数ⅠAのみだったり、BとCは数列とベクトルに限定されていることがほとんどです。
慶應では一応数Bも数Cも全範囲がテスト範囲として含まれていますが、基本的にはせいぜい部分的な出題でしょう。
おそらく大問1,2で小問の一つになることはあっても、大問として出題される可能性はあと1,2年は低そうです。
ただし、絶対に出ないとは約束できません。
難易度は典型的な問題ではありますが、各ジャンルの典型を複合させているので、慣れていない場合には見た瞬間わからなくなる可能性があります。
問題集(白チャートレベル:Amazonリンク)の標準的な問題だけでなく、難易度が高めの問題や章末問題もしっかり解いてください。
ただし、複合的な問題が基本となっているので、可能であれば全範囲をまんべんなく勉強してほしいところです。
最後は微積
基本的に最後は数Ⅱの微分積分からの出題になります。
大問4に微積が出題されることもありますが、基本的に大問3,4,5のどれか一つは微積の大問となります。
他の大学、他の学部でも最後が微積が最も多い形式です。
微積はパターンがある程度決まっており、グラフをイメージして、接線や法線を考え、面積を求めます。
微分を利用して、少し複雑さを加えた図形を図示する問題もよく出題されています。
普通の典型形式からひとひねりを加えていますが、難易度自体は標準的。
微積を根本理解していなくても、公式をしっかり覚えて、基本パターンを繰り返し練習することで十分に解くための実力をつけることができます。![]()
対策・勉強法
最初の2つの小問集合であれば、基礎問題精講(Amazonリンク)や白チャートなどの最も基礎的な問題集を2~3回するだけで十分にチャレンジできます。
しかも、問題集をまんべんなくではなく、難しい難易度の問題を2割程度は最初から解かなくても、小問集合には十分対応できるでしょう。
偏差値50~55程度の高校に通っている生徒であれば、しっかり復習をして学校の定期テストで70点くらいをとるイメージがわかりやすいと思います。
偏差値40程度でも1年~1年半あれば慶応クラスの看護を目指すことは十分可能です。
相性よく、正しい指導をする先生に出会えれば偏差値を短期間でも10伸ばすことは可能です。
大問にも対応できる力をつけよう
大問では、白チャートなどの問題集を基本的に全ページ解くイメージを持ってほしいです。
特に上記であげたよく微積とA、B、Cは章末問題などの複合問題も含めて3回程度は最低でも必要でしょう。
基本的な難易度はあくまで定期テストレベル。
日々の勉強や復習を正しく行えば特殊な勉強は全く必要ありません。
高校3年生になる前に一定のレベルに達していると非常に有利です。
大切なことはこつこつと基礎計算をしっかり身に着けることです。
それが大問に対応するための最大のポイントです。
まとめ
保護者の方へ
慶応大学の数学は私立看護としては非常に難易度が高いです。
一方で、全体的に基礎問題が多く、正しい勉強さえ積み重ねていれば攻略自体は難しくありません。
指導経験上、数学の勉強法を間違えている生徒が非常に多く、勉強方法を改善すれば現在の数学の成績が低くても慶応レベルの数学に対応できるようになります。
看護学科を目指す生徒には、勉強し始めるタイミングが遅い生徒が非常に多くみられます。
一般的な私立看護であれば、準備期間が比較的短くても対応できることもありますが、慶應だと非常に厳しいでしょう
ご家庭が早めに動き出すかどうかが合格の決め手になるでしょう。
看護学科に合格するための家庭教師なら → こちら
他の記事一覧は → こちら