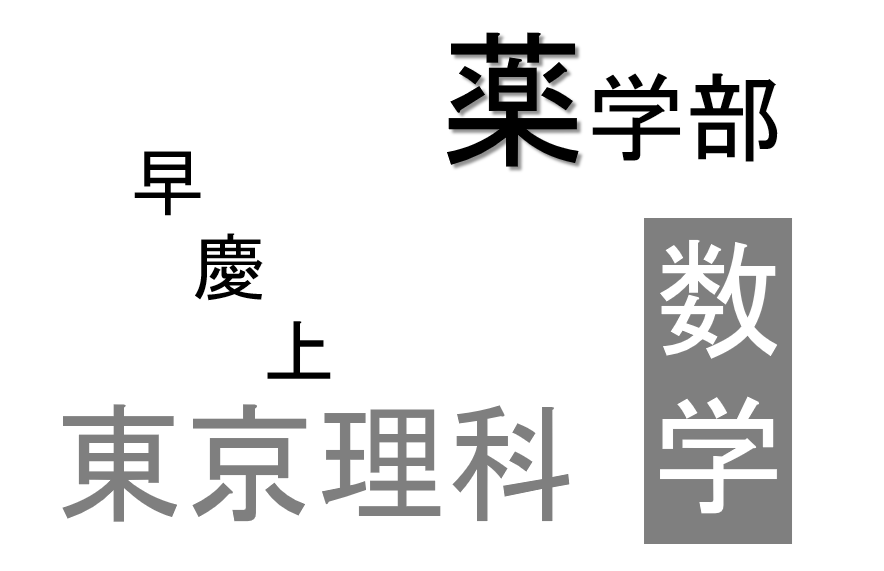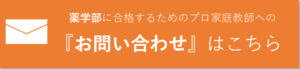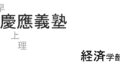薬学部の数学
理科大の薬学部では、
独自方式のみのB方式
独自方式 + 共通テストのC方式
の2種類。
どちらも独自の数学の試験があり、B方式が最も定員が多いメインの入試となっています。
他にも独自試験のない共通テスト利用のみの方式(A方式)もあります。
今回はメインの試験であるB方式の分析ですが、C方式でも活用できるようにしております。
範囲はⅠAⅡBⅢCで、 時間は100分。
A「図形の性質」「場合の数と確率」
B「数列」「統計的な推測」
C「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」
全編マークシート形式で、大問は4つとなっています。
薬学部分析 → 東京薬科大学 北里大学 京都薬科大学 星薬科大学 大阪医科薬科大学
他の大学分析は → こちら
薬学部トップクラスの難易度
私立薬学部の数学は、基礎分野の比率が高めの大学が多いですが、東京理科大では薬学部トップクラスの難易度となっています。
60~70%で合格できるので、大問1つまるまる落としても合格のチャンスは十分にあります。
薬学部受験では化学が最重要科目となりやすいですが、理科大では数学も非常に高い能力が求められます。
ただやみくもに勉強するのではなく、計画をたてて効率的に学習をすすめていきましょう。
特に集団指導塾を利用する際は、スケジュール管理をお子さん一人で行うので、注意が必要です。
出題傾向
理科大では、全範囲からまんべんなく出題されることが多く、分野を絞った勉強は危険です。
また、2025年1月からの新課程の範囲も広く、広範囲の勉強が必要になります。
他の大学ではほぼ100%出題される数BCからの出題がない年もあり、予測で動くのはやめましょう。
勉強が浅くなりがちな、数Aからの出題も多くなっています。
一方で、微積はほぼ確実に出題されます。
数Ⅲ比率は低くなっている
過去の入試では、4つ中2つの大問で数Ⅲが出題されたこともありました。
近年では数Ⅲからは大問1つの出題が通例となっています。
また、新課程で数Cになった複素数平面も比較的出題頻度が高め。
2024年は、
数Ⅲレベルの微積から1問
数Cの複素数平面から1問
数Cのベクトルから1問
と新課程の数ⅢCから大問3つ分出題もされています。
大問1は2~3つの分野に分割されることもあります。
数Ⅲは優先順位が明白
大問1つは微積が出題されると考えておきましょう。
100%ではありませんが、最も出題されやすい分野です。
数Ⅲの微積は極限も絡んでくることもあるので、
数Ⅱの微積
→ 極限の基礎
→ 数Ⅲの微積
という順番で勉強していきましょう。
微積の次に優先すべきが新課程で数Cとなった複素数平面。
前述したように、2024年は数Cの重要度が高く、2023年も複素数平面から出題がありました。
10年分の過去問をみると複素数平面の優先度は微分積分ほどは低くはありませんが、一定量の出題があり、重要分野の一つと考えて間違いないでしょう。
確実に取り組んでおくべきではありますが、時間がどうしても足りない場合は複素数平面だけにして、平面上の曲線を切り捨てるのも一つの戦略といえるでしょう。
数Aの重要性は圧倒的に場合の数と確率
数Ⅰや数Ⅱからの出題ももちろんあります。
数Bだって出題されています。
一方で、数Aと数Bは他のジャンルとの複合問題が多く、戸惑う受験生が多くなっています。
例えば数Bの数列は、数Ⅲの極限や数Aの図形と複合させた問題を作りやすいです。
また、数Cとなったベクトルも出題率は一定以上あるります。
近年の傾向を考えると、数ABで最も出題率が高いのが、数Aの場合の数と確率です。
2024年と2023年では大問1で出題されていました。
ただし、2022年の大問1は数Bの数列であり、2024年の大問1は場合の数と確率ですが、数Ⅲの極限も含まれていました。
その前の場合の数と確率は2019年までさかのぼることとなります。
一方で2021年には数Aの図形の性質が含まれた問題もありました。
共通テストやほかの薬学部では分野単独の問題が多く、理科大の合格を目指すのであれば、他の大学とは1~2ランク上の数ABの勉強が必要になるでしょう。
同じマーク形式でも共通テストとは出題傾向が大きく異なるので、注意が必要です。
大問1つは難問になるかも
最初の大問は基礎的な計算問題が一部出題されることがありますが、 大問2以降のどこかで、難易度が高い出題がされた年もあります。
制限時間60分前後の大学が多い中で、東京理科の薬学部では100分。
難問で大幅に時間を使ってしまうと、時間が不足するでしょう。
100分と長く見えますが、意外と余裕はありません。
また、一つ一つの計算ボリュームがかなり大きいので、入試が近づいてきた時期をみて理科大のための時間配分の練習が必須となっています。
プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら
全記事一覧は → こちら
難問は数Ⅲ以外の可能性が高い
年によって、難問が出ないときもあります。
難問が出題される場合は、過去の傾向では数Ⅲ以外の分野が多くなっています。
私立の薬学部は、多くの大学で数Ⅲが範囲外。
難問対策として数ⅠAⅡB + ベクトルをしておけば、東京理科の対策になるだけでなく、併願校対策としても有効だといえます。
計算には細心の注意を
微積の問題にはeや三角関数が基本であり、 絶対値の出題もあります。
確率でも4桁5桁が出てくるなど、単純に数えるだけでは通用しません。
一方で6割とれば合格が見えてくるので、計算ミスが0であれば合格率は飛躍的に高まるといえるでしょう。
参考書・問題集
普段使う問題集としては、青チャート(Amazonリンク)かニューアクションレジェンド(Amazonリンク)が最適です。
偏差値55~60くらいでよく用いられる4stepなどはあまりおすすめできません。
青チャートやニューアクションを使う場合は、全国模試(数学の受験者3万人以上)で偏差値60くらいは取っていなければ、レベル的に合っていないといえます。
東京理科大学はチャレンジ校の位置づけで、メインは北里や立命館、星薬科や明治薬科の場合は、青チャートは難しすぎるといえます。
黄チャート(Amazonリンク)でも確実に合格点がとれる難易度です。
現実的に考えると、黄色チャートの方が効率的に勉強できる生徒が圧倒的に多いはずです。
大学を基準にして問題集を選別しがちですが、最初は自分の実力を基準にして問題集を選びましょう。
特に数Ⅲは、他の分野と比較すると難問が出題されにくいです。
黄色チャートだけでも正しく真面目に勉強すれば、間違いなく合格点がとれます。
家庭教師や個別指導塾など、自分(お子さん)のことをしっかり分析してくれる人のアドバイスを大切にしましょう。
理科大(Amazonリンク)分析よりも、まずは自己分析です。
まとめ
保護者の方へ
日本で有数の私立大学である理科大は、数学の難易度がかなり高いです。
薬学部に合格するのであれば、遅くとも高校2年の夏には受験生としてエンジンをかけ始める必要があります。
高校の偏差値が60以下であれば、高校1年の段階から少しずつ勉強を進めて、高校で課される水準よりも高いレベルを常に目指し続ける必要があるでしょう。
理科大の薬学部は浪人生も多く、非常に難易度が高いです。
お子さんがのんびりして、危機感をなかなか高められていないのであれば、保護者の方が積極的に背中を押してあげてください。
薬学部・理科大に合格するためのプロ家庭教師の指導は → こちら
他の記事一覧は → こちら