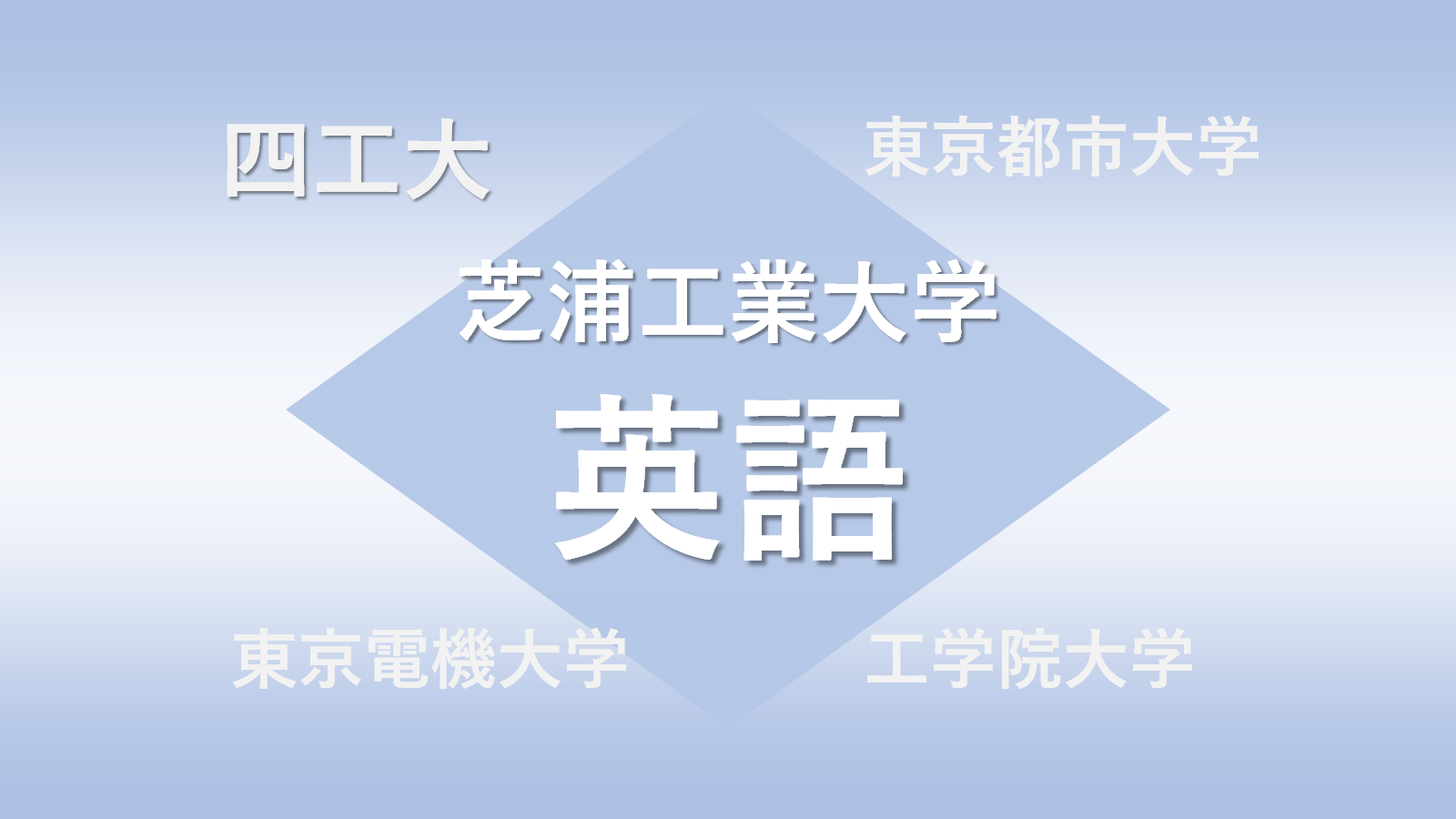芝浦工業大学の英語
芝浦工業大学のメインの入試は前期と全学部統一。
2025年は、
前期はAとBの2回
全学部統一もAとBの2回
が予定されていましたが、その両方で英語は外部試験を利用することとなりました。
芝浦工業大学独自の英語試験は廃止となりました。
外部試験には共通テストが含まれており、共通テストの利用幅を縮小する大学もあるので、2026年以降に独自試験の英語が復活する可能性もあります。
理科に大きな変化はありません。
数学はⅢC(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面)
数Bは数列のみ 統計は入らない予定です。
どの学部学科も問題は共通で科目も基本的に同じですが、今回は最も定員が多い前期日程の英語分析になります。
総合型でも、英語外部試験のスコアが要件に入っています。
小論文や面接もほぼ必須です。
その他の大学分析(全記事一覧)
大問数が普通より多い
最初の特徴としてあげられるのが、大問が8~9つと多いこと。
今回は前期日程ですが、実は全学部統一でも大問数は同じくらいの数となっています。
時間は90分。
大問1つのボリュームが多いものと少ないものが混ざっています。
全体としては90分であれば十分に消化できる分量。
大問が多いからと焦って早く処理しようとすると、拙速となり点数が伸びません。
傾向分析は必須といえます。 最初は時間制限なしで、なおかつ時間をはかってみましょう。
1~5まで文法問題
最後の2つの大問を除いて、基本的に文法問題や短い会話文からの出題になります。
種類の違う問題が続く雰囲気は過去のセンター試験に近く、共通テストでも一部似ている試験があります。
実際には多様なタイプの問題が出題され、毎年傾向が少しずつ変化するので、様々な対策を行うことが有効です。
高校1年生から少しずつでいいので受験を見据えて対策ができます。
現在の偏差値が40くらいでも、盤石の状態で芝浦工業大レベルに到達しやすくなるでしょう。
表面的な傾向に惑わされないように、本質的な英語読解力と現代文を合わせた能力が必須といえるでしょう。
文法問題のタイプをおさえよう
主に文法系の問題が5つ出されます。
対面授業もオンライン授業も、プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら
オンライン(ウェブ)授業のご説明は → こちら
全記事一覧は → こちら
基本文法に注目
ベーシックな4択の文法問題。
基本的に10題が1~2セット出題されます。
2セット出題される場合は、最初の10問は単語よりの問題が出題されます。
文法的な紛らわしさよりも、単語力、熟語力が勝負。
英単語は長文で問われる大学も多いですが、芝浦は直接4択で問われます。
特にスペルが似ているけど、意味が違う単語もよく出ているので、確認しておきましょう。
もう一つ必ず出題されているのが、並び替え問題。
私大の英文法問題として頻出。 こちらもしっかり対策が必要です。
会話文はここ2年の大問1
4択や並び替えはほぼ100%どの私大でも出題されますが、会話文は大学によってかなり差があります。
少し前ですが、2018などは出題がありませんでした。
ここ数年は大問1で会話文を5題が定番となっています。 難易度は高くなく、標準的。
ただし、会話でよく使われる表現が文章にも選択肢にも混ざっているので、 会話表現が入っている問題集で対策する程度は必要でしょう。
2文が同じ意味になるように
芝浦で特徴的な問題が、適切な単語の書き換え問題です。
名詞を形容詞に変えたり、動詞を名詞に変えたりなど、 単語の品詞を変更する問題になっています。
選択ではなく実際に記載する必要から、スペルを正確に書かなければいけないと同時に、 品詞の微妙な違いを理解しておかなければいけません。
工学系や建築系など、最初から芝浦を受験する可能性がある生徒は、単語の勉強の時点で品詞にこだわっていきましょう。
短めの長文
大問6や、たまに大問2で、100語前後のボリュームの文章が出題されることがあります。
大問3に出題された年もあります。
合計で50~100語程度になるような、短文の並び替えなどが出ることもあります。
2023、22、21年などは、図表とセットでの短め長文が増えました。
共通テストの影響を受けているのかもしれません。
また、図表も円グラフや棒グラフといった分かりやすいものだけでなく、 リスニング等でも使われるような、簡易地図も出されたことがありました。
年によって位置も形式も変わってくるので、予測ではなく正しい英語力をつけて、 どのような問題でも対応できるようになりましょう。
大問7は短めの文章
大問2や6のように、大問7も年によって変わる文章問題になります。
ただし、全体のバランスをみて、200語程度のボリュームになることもあれば、100語を下回る分量のこともあります。
また、出題形式も年によって変化するので、こちらも柔軟性が求められます。
最後の長文と違って単語もセンターや共通テストレベル。
出題形式も緻密に読みこむよりも、接続詞や大体の流れがわかることで解答できるものが多いので、 そこまで構える必要性はありません。
文の並び替えが出題されやすい傾向にあるので、 同様の問題の練習を行えば、そこまで抵抗なく取り組めるでしょう。
文法の単語並び替えとは一見似ていますが、勉強法が異なるので注意が必要です。
あくまでメインの長文は大問8と9になります。
ただし、8は短めで、単語や接続詞などが中心となったり、長文を段落ごとに並べ替えるパターンもありました。
大問8と9の両方でしっかりとした長さの長文読解となったこともあります。
メインの長文は大問9(と8)
これまでの問題とことなり、しっかりとしたボリュームがある、総合的な出題がされるのが大問9の長文です。
内容がまさに理系。
実験があり、典型的な理系文章になっているので、構成自体は読みやすく、長文読解テクニックが使いやすくなっています。
ただし、単語力が一定以上求められることと、和訳があることが特徴。
また、問題量から推定すると、内容把握の点数比率がかなり低いことから、長文はあまり読めなくてもいいのかもしれません。
理系の大学生として、英語の論文を読むことを考えると、かなり不思議な気がします。
芝浦に合格した生徒は、入学前や大学1年目に英語を鍛えなおすことをおすすめします。
ここでも序盤は文法や単語の穴埋め
大問1~6で多くの文法問題が出題されたにも関わらず、長文の空欄に単語を補充する、 長文中の文法問題が、こちらの大問でも出題されています。
正直いってやりすぎなくらい文法を出題していると思いますが、 受験生からすると対策しやすく、取り組みやすくなっていると思います。
まとめ
保護者の方へ
芝浦工業大学の英語は様々なタイプの出題があります。
多くの文法問題に加えて、図表と理解を問う長文。
ただ和訳が出来れば合格点が取れるわけではなく、国語と複合させた理解の英語が必須となります。
単語や文法を覚えるだけ、英文を和訳するだけの教科書をつかった機械のような英語では合格は難しいでしょう。
一方で自己分析に基づいた正しい英語を進めれば、合格点をとることは難しくありません。
芝浦は英語だけでなく数学や理科(物理・化学)も難易度が高いので、3科目総合で指導してくれる質の高い先生がいれば有利です。
お子さんの成績を単一科目や短期的視点だけで評価することはお控えください。
英・数・理の3科目を指導するプロ家庭教師に興味がある方は → こちら
他の記事一覧は → こちら