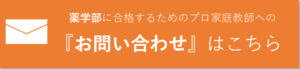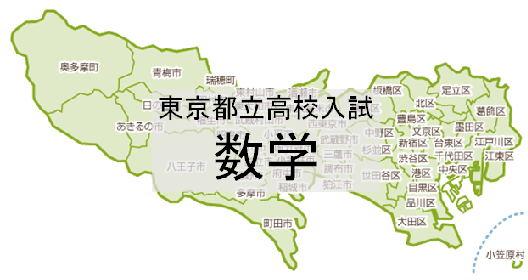薬科大学の化学
東京薬科大学では、化学の独自試験があるのはB方式とT方式。
B方式がメインの学部別試験。
定員も120名と大きく、志望度の高い生徒が絶対受験すべき方式です。
T方式は定員40名で、薬学部と生命科学部の両方で問題が同じとなっている統一選抜となります。
他にも、総合型(旧AO)や推薦も枠が大きいのも特徴です。
本分析ではB方式をメインで扱いますが、T方式も傾向は近いのでどちらにも使えるように作成しています。
穴埋め問題
共通テストや旧センター試験のように穴埋め形式になっています。
数学と同様に化学でも穴埋め。 一般問題は5択になっています。
計算問題も選択式ですが、6択です。
化学の重要性が最も高い
B方式では化学は150点の配点ですが、英語と数学は100点ずつ。
T方式に至っては化学200点に対して、数学100点で英語なしです。
薬学系の大学ではよくあることですが、化学が合否にもっとも影響する科目となっています。
化学の力さえ高めておけば、合格が一気に近づきます。
現在の学力に自信がなくても、1年~1年半くらいしっかり勉強すれば合格可能性を飛躍的に高められるでしょう。
薬学部分析 → 東京理科大 昭和薬科大 星薬科大 昭和大 大阪医科薬科大 京都薬科大 神戸薬科大
他の大学分析は → こちら
最初は小問集合
大問1は8問の小問集合。
これはB方式でもそうですが、T方式でも同様の傾向です。
全てが独立している年もあれば、 小問が2~3問続きになっている場合もあります。
全ての大問で一番難しくないので、ここが半分も解けないのであれば、勉強を根本からやり直しましょう。
暗記の1問1答が中心
小問であり、一つ一つは独立して考えることで解答を導き出せます。
化学基礎での内容から出題されています。
理論化学ではイオンや原子分子、結晶といった最初に習う内容がほとんどなので、いかに基礎力を正しく積み上げていくか?が問われています。
加えて、無機化学と酸化数もよく出題されます。
復習のタイミング
薬学部を目標にすることが早めから決まっているのであれば、高校2年のお正月までには化学基礎は完璧にしておきましょう。
化学基礎自体は、高校1年生のときに一通り終わっているはずなので、
復習のタイミングを自分で作る
家庭教師や個別指導塾を利用する
のどちらかがよいでしょう。
今はオンライン授業(web授業)もあるので、地方に住んでいても都市圏の先生を見つけることも可能です。
中高一貫校では、中学時代に化学基礎が半分くらい終わるので、高2になってようやく復習を始めると、1年以上間が空きます。
勉強の予定管理を徹底しましょう。
残りの大問は分野別
大問2~5は、分野別の大問です。
全分野から出題され、まんべんない勉強が必須です。
大問2はシンプルな計算中心
酸化還元
酸塩基
といった化学基礎でも勉強すると同時に、化学でも重要な計算問題が中心となりやすいです。
pHや水のイオン積、電池や電気分解といった化学基礎の計算のオンパレードです。
年によって微妙に違いますが、計算といっても比較的シンプル。
基礎~標準レベルの力を高めるだけで、満点に近い点数が無理なく取れます。
合格最低点を考えると、大問1,2でしっかり点数を取っておきましょう。
酸塩基は出題されやすい
ここ数年をみてみると、最後の有機化学に次いで出題されやすいのは酸塩基です。
もちろん、出題されていない年もあります。
他には、熱化学、電池電気分解、化学平衡といった定番だけでなく、
浸透圧や固体の溶解度といった他の大学では出題頻度の低い分野も出題されています。
大問1で無機化学の出題量が多いことから、大問2以降で無機化学の出題はあまりありません。
大問3以降でも計算必須
それぞれの大問で、基本的に複数の計算が出題されます。
大問3では化学基礎よりも気体や、温度と圧力といった化学に関する計算が増えます。
この辺りは
計算の難易度は変わらず基礎~標準となっており、計算式も複雑なものはありません。
数学的な難しさよりも、現象そのものを考える化学の難しさがあります。
化学変化の理由をきちんと理解しておかないと回答が作りにくいので、 暗記ではなく普段から理解中心で化学を勉強しなければいけません。
最後は有機化学
最後はおなじみの有機化学。
大問でいうと4,5は有機化学からの出題です。
難易度は大学受験としては標準的ですが、私立薬学部としては難しいです。
有機化学は出題パターンが比較的限定的で、対策がしやすいです。
一方で高分子化合物などややこしく覚えにくい暗記が混ざり、苦手な生徒も少なくありません。
効率的で正しく勉強することで、有機化学は一気に得意分野となります。
難問ではなく、標準的な難易度の有機化学を、あなたに合った方法で理解させてくれる先生がいるだけで、大きな成長を実感できるでしょう。
正しい勉強をすれば、東京薬科の最後の問題で間違いなく点を取れます。
構造式から理解
有機化学では物資の化学的な変化はもちろんですが、
組成式・分子式・構造式
の理解が必要です。
とくに構造式に関する出題はほぼ毎年出題されています。
構造理解は大学によって出題される、されないが分かれやすい分野。
東京薬科を受験する可能性があるのなら、しっかり理解しておきましょう
高分子化合物は比率が低い
大問5では、有機化学の後半である高分子化合物から出題されやすくなっています。
大問4の基礎を支える重要な有機化学に対して、大問5は出題数が少なく、暗記中心の出題となっています。
暗記自体は結構複雑で大変ですが、理解の難しさは基本の有機化学が出来ていれば問題ないでしょう。
ただし、一般的な高校のペースだと高分子化合物の勉強がぎりぎりになって復習の時間がしっかりとれないということが起こりやすいです。
塾や教科書のペースではなく、自分自身の理解と志望校の分析に合ったペースでの勉強が必須となります。
参考書・問題集
基礎~標準レベルをしっかりと理解できる参考書がおすすめです。
宇宙一わかりやすい高校化学(Amazonリンク)
化学の新研究(Amazonリンク)
岡野の化学(Amazonリンク)
などが候補としてあるでしょう。
難関薬学部である東京薬科(Amazonリンク)の名前に負けて、難しすぎる参考書や問題集を選ぶ生徒がいるので、間違えないように注意してください。
何度も言いますが、基礎~標準レベルを固めることが最優先であり、合格への近道です。
問題集
学校レベルの問題集を中心にすることがよいでしょう。
奇問難問が出題されないので、標準的な問題集を繰り返しとくことが重要です。
浪人生などでも間違える生徒が多いですが、メインの問題集は1冊で大丈夫です。
既に持っているものを使うといいですが、3回以上解いて、かなり覚えてしまっていて不安な場合には、別の問題集を買ってみてもいいでしょう。
共通テストも使いやすい
出題形式や、全般的な出題、標準レベルの難易度を考えると、復習に共通テストを利用することもできます。
赤本は3年生の9~12月ごろを目安に解いていくといいでしょう。
生徒の学習進度によって前後するでしょう。
化学は集中的に対策をしても効果があるので、一定の基礎学力があれば受験の半年前でも大幅に点数を増やすことができます。
まとめ
- 基礎~標準レベルで合格できる
- 大学入学後まで考えた勉強法
- 化学基礎の復習を忘れずに
保護者の方へ
化学は薬学部での最重要科目であり、東京薬科でも同様です。
大学受験に必須の科目というだけでなく、大学入学以降でも最重要科目。
単純に点が取れるのは当たり前であり、その先まで見据えた理解の習慣が必要です。
ご家庭としても、お子さんにぜひいい先生を用意してあげてください。
最終的にお子さんのためになりますし、経済的でもあります。
薬学部に合格するためのプロ家庭教師の指導は → こちら
他の記事一覧は → こちら