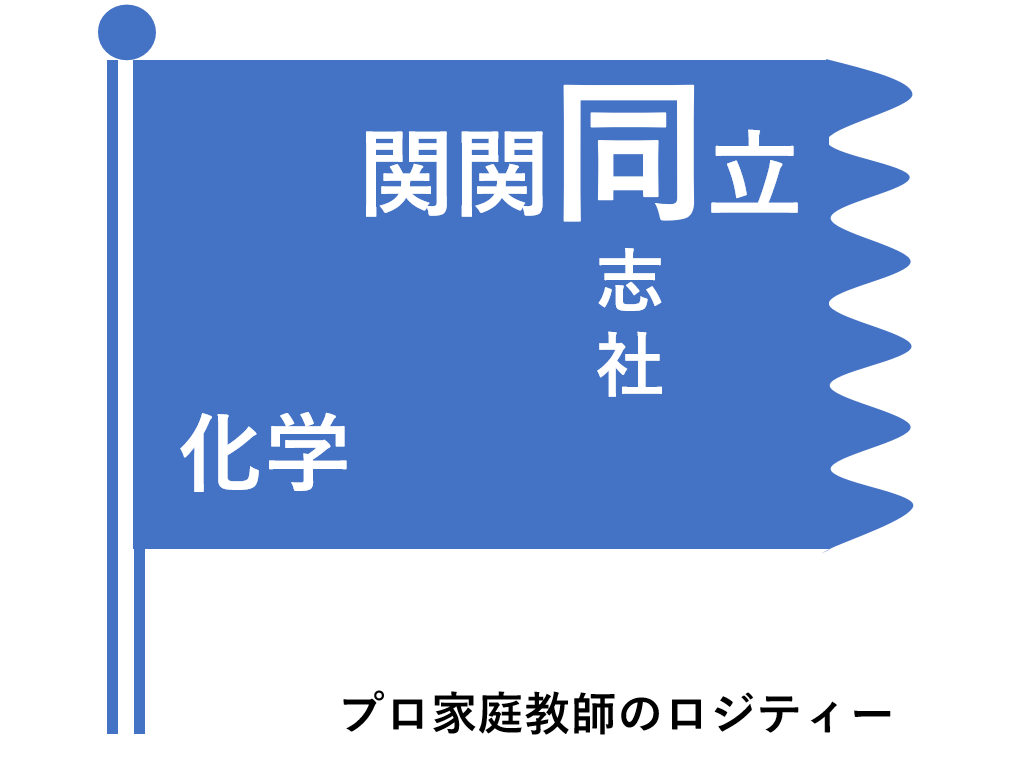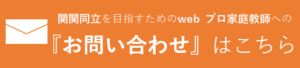同志社大学の化学
同志社大学の学科試験には
一般選抜入学試験(全学部日程:理系と文系に分かれる)
一般選抜入学試験(学部個別日程)
共通テスト利用入試
の3種類があります。
本分析は 一般選抜入学試験(全学部日程:Amazonリンク) の化学のものですが、学部個別日程でも役立つように作成しています。
定員は基本的に全学部日程と学部個別日程でほぼ同数もしくは統合なので、重要性は同じと覚えておきましょう。
よくある質問・料金などは → こちら
全国どこでも授業が受けられるオンライン授業に関しては → こちら
全学部日程
化学が試験科目にある理系学部(全学部日程)は
理工学部(9学科)
文化情報学部
生命科学部
スポーツ健康科学部
心理学部
となっています。
理工学部(Amazonリンク)の機械システム工学科のみ理科は物理が必須で化学が選べません。
同志社大学分析 → 理工学部 理系数学分析 生物分析 経済・商・政策学部
関関同立分析
他の記事一覧は → こちら
学部個別日程
学部別の試験で化学が選択できる学部は、
文化情報学部(理系型)
スポーツ健康科学部(理系型)
理工学部(9学科)
生命医科学部
となっています。
配点の違いに注意
全学部日程において、理科の重要性は普通か少し低め。
理科(化学・生物・物理)の配点は150点もしくは200点(学部によって違う)。
英数が200点がどちらも200点なので重要性が変わります。
一方で個別学部日程は重要性が高まります。
多くの学部で理科が150点もしくは200点に対して、 英語が100点、数学が200点。
どちらの日程を受験するとしても、重要な科目の1つであることは間違いないでしょう。
各大問で出題率がだいたい決まっている
75分で大問は3つ。
つの大問あたりの文章量がそこそこあり、実験形式なので読みごたえがありますが、正しい勉強が出来ていれば時間が不足する可能性はほぼないでしょう。
基本的に、
大問1が無機化学と理論化学の複合
大問2が理論化学
大問3が有機化学
で、実験の難易度が高め となっています。
ただし、2023は大問1と2の出題順番が例年の逆になっていました。
大問1が最も暗記要素が強い
大問1は
(1)が長文内の空欄補充
(2)が無機化学の選択問題 となりやすく、知識が続きます。
(3)では化学反応式やイオン反応式
(4)と(5)で理論化学に寄った問題 が出題されます。
出題年によっては(6)(7)も出ることがありますた、一つ一つが独立した理論化学の問題となりやすいです。
大問1は無機化学と無機化学に関連させやすい化学基礎の理論化学の出題率が高いです。
得意不得意の偏りが小さい生徒では、最も安定して点が取りやすい大問でしょう。
大問1の点数が低くなる生徒は勉強方法が大いに間違っている可能性が高く、化学基礎から復習しなおす必要があります。
理想をいえば、高校1年生の間に正しい勉強方法を身につけるか、正しく導いてくれる質の高い先生に出会うことでしょう。
判定の目安の一つとして、化学基礎の模試で偏差値55~59は要見直し。
55未満は即座に改善が必須と考えましょう。
ちなみに、偏差値60あれば大丈夫というほど簡単な話ではありません。
同志社のレベルはそれほどまでに高いということを知っておきましょう。
大問2は理論化学の中でも難しい
大問2は理論化学(Amazonリンク)の中でも理論自体の理解が難しく、苦手な生徒が多い分野から出題される可能性が高いです。
実際最も点数が取りにくい大問といえます。
化学反応と化学平衡・気体・コロイド・浸透圧・溶解度 といった分野が多いですが、特に反応速度と化学平衡から出題されやすいです。
実験の流れに惑わされない
大問2は大問3の有機化学とは異なり、実験の流れがそこまで重要ではない年も多くあります。
注意してほしいことが、年によって違いが大きいということです。
難易度が高いものの、一問ずつ独立とまでいかないものの、切り分けやすい部分があります。
(2)が解けなくても、(3)が解ける可能性は普通にあります。
計算問題も多いですが、難易度は極端に高いということはなく、標準レベルも多くあります。
慎重に時間をかけて、ひとつひとつ読み解いていきましょう。
年によって差が大きいですが、質の高い先生と一緒に分析すると突破するポイントがわかるような問題です。
受験が近くなると戦略的思考も重要になる
合格最低点と解きやすさを考え、大問2は最後に解答する、そもそも満点を狙わないといった戦略も重要になります。
生徒の得意不得意にもよりますが、多くの生徒にとっては、有機化学中心の大問3の方が安定して高得点を狙いやすいでしょう。
最後は有機化学
大問3は有機化学もしくは高分子化合物(有機化学の一種)のどちらかから出題されます。
暗記要素の強い高分子化合物は出題率が低いですが、2021、2019年など過去に出題されています。
2023、2024などの近年では王道の有機化学が出題されています。
同志社クラスを目指すのであればどちらも高いレベルにしておくことが必須でしょう。
暗記は理解が不足しているとほぼ不可能
有機化学も高分子化合物も、
化学基礎における粒子や結合の理解
主に理論化学における化学反応式の理解
有機化学の基本的理解
の3つが揃っていないと、暗記すら上手くいきません。
逆に言えば、理解が出来ていれば暗記も効率的にできますし、入試レベルの実験手順も恐れることはありません。
高校3年生で有機化学(Amazonリンク)を勉強する生徒が多いですが、入試レベルの有機化学で点が取れるかどうかは、高校1年の化学基礎で半分くらいわかってしまいます。
特に関関同立や早慶、SMARTレベルでは、はっきりと差が出ます。
実験理解が計算理解につながる
ハイレベルな有機化学で点数を取るには、実験理解が必須。
しかし、実験手順は実は難しくありません。
実験問題は苦手、という生徒がいますが、そのうち7割くらいの生徒が基礎力の不足であって、実験問題に入る手前に問題があります。
残りの生徒は国語(現代文:論理国語)に問題があり、科目複合的な指導を受けていないことが原因です。
実験理解に必要な読解力は、同志社クラスの受験生にとって英語・数学でもある程度は必須。
ここの能力が不足していると大幅に不利といえるでしょう。
どちらもそろえば、有機化学で難しいといわれている実験問題は、一気に点が取りやすい分野へと変化します。
高分子化合物の場合は、理解も大切にしながら、暗記の部分と分けるか、複合させるか、を生徒の性質に合わせて教えてあげれば、比較的短時間で対策が完了します。
計算は難しいが、そこまで複雑ではない
化学の計算はそもそも難しい問題が非常に少ないです。
同志社の有機化学における計算も一見複雑ですが、化学計算のポイントを理解していれば理系ならだれでも解ける難易度に設定されています。
数学はそこそこできるのに化学の計算が苦手な場合は、やり方に大いに問題があるでしょう。
そもそも高校の数学が苦手という生徒は理系数学の勉強方法を間違えていますし、化学で必要な数学力は中学生レベルです。
数学に自信がなくても正しい先生の指導をうければ、同志社レベルの化学計算に恐れることはありません。
参考書・問題集
同志社の化学は難しいですが、必要とされている理解や知識は一般的な高校化学です。
特別な参考書や問題集は不要です。
宇宙一わかりやすい高校化学(Amazonリンク)
化学の新研究(Amazonリンク)
ゼロから劇的にわかる(Amazon リンク)
ただし、100%に近い、高いレベルでの理解が求められます。
しっかり理解してから問題集という王道の勉強方法を身につけなければ合格は難しいでしょう。
問題集
セミナーやリードα(もしくはリードlight)などが最初の問題集となるでしょう。
セミナー化学(Amazonリンク)
リードシリーズ(Amazon リンク)
チャート式 新化学(Amazonリンク)
最初の問題集が8割くらい出来るようになれば、
重要問題集 もしくは 標準問題精講
まとめ
保護者の方へ
同志社大学の化学は、関関同立でもトップクラスに難易度が高く、日本中の私立大学でも最上位レベルに入るでしょう。
問題は難しいですが、王道の問題として難易度を高くしているので、特殊なことをする必要はありません。
化学における基本理解を徹底し、典型問題を中心に力を高めていけば自然と合格が見えてきます。
同志社クラスは化学だけでなく他の科目もハイレベル。
本格的な勉強は遅くても高校2年生の夏にはスタートさせましょう。
プロ家庭教師の指導に興味がある方は → こちら
他の記事一覧は → こちら