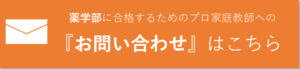星薬科の数学は標準レベルがメイン
星薬科大学の数学は、大問が6つあります。
2025年1月以降の新課程でも、範囲はⅠAⅡBC
(B:数列、C:ベクトル)
2025年2月の試験でもこれまでの傾向と基本的に変わりませんでした。
小問集合はなく、一つ一つの大問のボリュームがかなり少なめ。
80分あるので、正しい勉強を継続していれば、時間が不足する可能性は非常に低いといえます。
ただし、勉強法を間違えていたり、事前の過去問分析が不十分な場合は、時間が足りなくなるでしょう。
あくまで目安ですが、 数ⅠAから3問前後 数ⅡBCから3問前後 に設定されています。
他の大学分析は → こちら
標準的な内容が多い
各大問は(1)~(3)くらいまであることが多いですが、(1)は非常に点数が取りやすくなっています。
2023や2022は(2)までがほとんどでしたが、(1)が長めになっていました。
2025年の入試も(2)までの大問が3つあり、(3)までの大問も3つでした。
どの大問でも(1)は必ず見たことがある標準的で、典型的な問題。
そして、一部は基礎的で公式をそのまま使うだけ。
数学に自信がない生徒は、各大問の(1)を満点にする勉強を心掛けましょう。
全範囲を網羅的に勉強しよう
薬学部の数学は、大学によっては出題範囲に偏りがありますが、星薬科大学では偏りが少なくなっています。
他の大学では出題頻度の低い
データと統計
整数の性質のn進法
数Ⅰレベルの2次関数と絶対値
などの分野が時々出題されています。
数Ⅰのデータと統計は様々な大学で存在感を高めており、基礎~標準レベルを中心として出題する大学では出題率が高まっています。
ここ数年は星薬科では出題がありませんが、時間に余裕があれば一定の対策をおすすめします。
分野を絞らずに、高校1年、遅くとも2年生の夏ごろからしっかり復習して積み上げた生徒が非常に有利になります。
逆に受験生は高校3年生から、と思っていると浪人する可能性が高まるといえるでしょう。
数ⅠAで点が取りやすい頻出範囲
星薬科で狙いたいのは、
2次関数
場合の数・確率
数学と人間の活動(旧:整数の性質)
の3分野です。
どれもⅠAで早くから復習がしやすく、難易度が高くない問題が多めになっています。
大問1が数Ⅰ
大問2が数A
から出題されるのが定番です。
数Aの範囲に注意
数学と人間の活動(旧:整数の性質)は数Aの範囲ではありますが、2025年1月からの新課程入試では、共通テストや一部大学の入試では範囲外となります。
星薬科は新課程でも数Aは範囲指定がなく、数学と人間の活動も範囲内の前提でしょう。
もしかすると今後は出題率が下がるかもしれません。
勉強方法に注意
上記の3範囲は、苦手な生徒が非常に多いです。
ですが、そのほとんどが勉強法を間違えているだけで、理解中心の勉強方法に切り替えるだけで大きな改善ができます。
目先の点数ばかり追っていると理解ができず、暗記の数学になりがち。
小論文や国語の勉強を中学、高校1年で取り組んでおくと一気に有利になるでしょう。
数学でも一定量は暗記を活用して構いませんが、微積も絡む2次関数や、小学生の理解が有効な確率・整数は理解をおすすめします。
いい先生に習えば確実に理解できます。
数BCは確実に出題
かつての大問6はほぼ確実に数BCの両方が出題されていました。
(1)と(2)にわかれており、片方が数列で、もう一方がベクトルです。
ただし、ここ数年は中問集合のようになっており、最後の大問は片方が数列もしくはベクトルで、もう片方が別の分野からの出題が増えています。
解答作成の流れを考えると典型問題とはなっていますが、一定の難易度があります。
基礎レベルだけでは完答は難しく、標準レベルを網羅する必要があります。
対策が早くからできれば、美味しい点取り問題です。
しかし、現実的には化学や英語など他の分野や科目に時間がかかると、数BCの勉強不足になりやすいといえます。
家庭教師や個別指導塾を活用する場合は、スケジュール管理まで自分に合わせてくれる先生にしましょう。
![]()
プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら
全記事一覧は → こちら
微積は対策がしやすい
大問5は高確率で微積です。
微積単独の大問になることもあれば、若干別範囲と複合させる出題もみられます。
薬学部は大学で学ぶ内容の特性上、どの大学でも微積が出題されやすくなっています。
微積は大問1~4と比較すると、受験生がちょっと苦手と感じそうな問題があります。
実は微積はパターンが少なく、星薬科の問題も分析上手な先生に習うと、短期間でも成果が高い勉強ができるでしょう。
数Ⅰの2次関数の勉強を先に済ませることを忘れないでください。
ほかの数Ⅱは時間がかかる
数Ⅱからも出題される可能性が非常に高いですが、どの分野がでてくるのかは予想が難しいです。
大問3と4は数Ⅱの微積以外の分野から出題されています。
満点を狙う必要はなく、得意な分野でしっかり点を取るために、ある程度優先順位をつけて勉強をすすめましょう。
数Ⅱも他の分野と同様に、標準的で典型問題ばかり。
色々な分野を同時並行で勉強するより、基礎は分野を決めて勉強を行うことをおすすめします。
参考書・問題集
メインの問題集としては黄色チャート(Amazonリンク)レベルがおすすめです。
白チャート(Amazonリンク)でも、しっかり頑張れば合格点を取ることができます。
星薬科が第一志望で、それ以上に数学の難易度が高い学校を受験しないのであれば白チャートや基礎問題精講などで合格に到達できるでしょう。
過去問で傾向分析は役立つ
上記のように、各大問でどの範囲が出るかは比較的読みやすいです。
過去問(Amazonリンク)は早めに一度試して、レベルと範囲を理解しておくととりくみやすくなっています。
まとめ
保護者の方へ
薬学部を目指しているお子さんでも、数学に苦手意識がある生徒は多いです。
薬学部の数学は難易度がそこまで高くありませんが、星薬科ではいかに早くから対策を始めるかで勝負が決まるといえます。
現在のお子さんの数学の偏差値が35~45くらいだとしても、高校2年生から質の高い先生の指導を受ければ合格は普通に見えてくるでしょう。
具体的に勉強を教える必要はありませんが、 保護者の方がお子さんの状況をこまめにチェックしてあげてください。
薬学部(国公立・私立)に合格するためのプロ家庭教師の指導は → こちら
他の記事一覧は → こちら