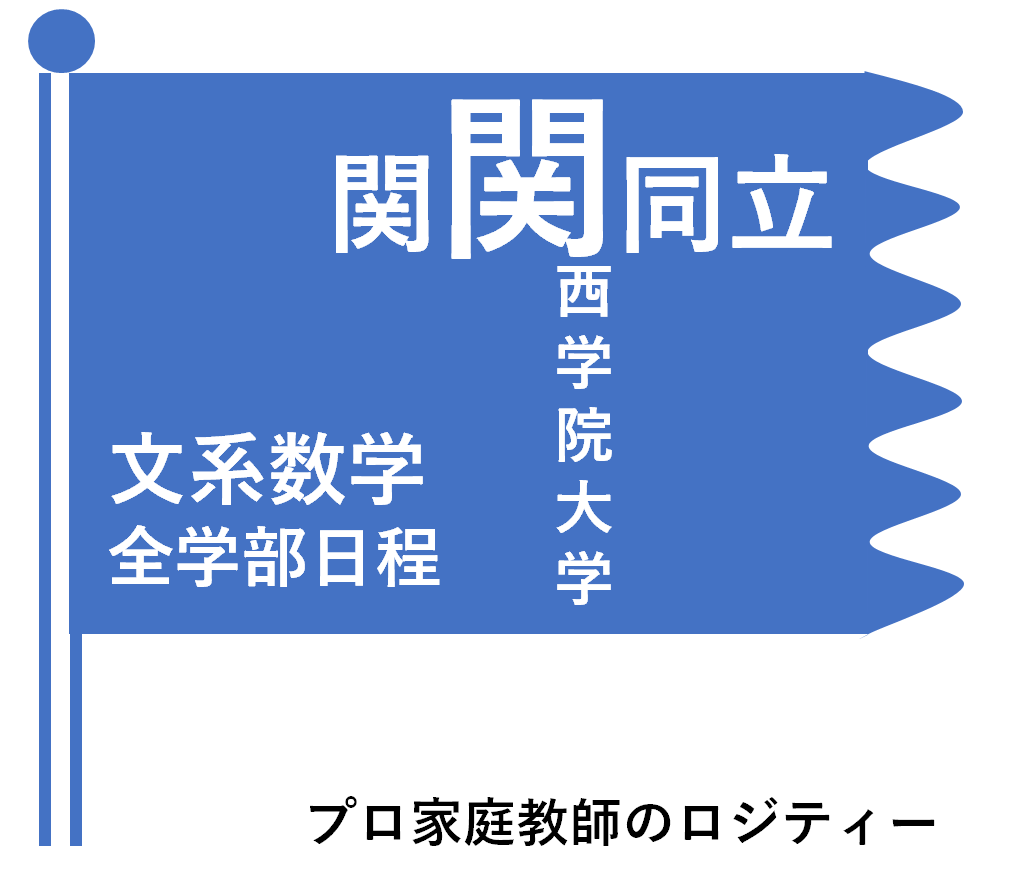千葉県の高校入試の社会は最も対策が重要な科目
近年は理科と合わせて社会も思考問題が増えました。
図表や写真問題も多く出題され、知識だけでは解けない問題が増え、より実践的な変化をとげています。
これは、全国的な傾向で、今後も継続・拡大することが見込まれています。
「社会は暗記」は部分的にしか合っておらず、「社会は暗記と思考の組み合わせ」という考えが必須です。
思考問題には国語力も重要になります。
家庭教師などを選ぶ際には、国語と社会を同じ先生に教えてもらうことが理想的です。
8つの大問のバランスに注意
かつての大問数は7つでしたが、ここ3年は大問数が8つになりました。
社会もそうですが、小学生や中学生の学習内容が増加し、大問も増加傾向。
学ぶことが多いので、中学生は以前より計画的かつ蓄積がえられる勉強法が必須となりました。
出題傾向も重要ですが、1年生や2年生のときから勉強方法を見直して、学習の質を高めることが最重要です。
傾向は明白だが、量が多いので対策は大変
8つの大問のうち7つは、
地理
歴史
公民
がそれぞれ2つずつ出題され、 追加で公民色の強い国際社会関連の出題が多くなっています。
さらに、大問1では地理・歴史・公民の全ジャンルから一問一答形式の問題が出題されています。
国際的な部分は中学校の勉強では社会に分類され、近年の戦争に関する話題が入試に入りやすくなりました。
また、2025年には高校生での情報という科目に入る様な、生成AIに関する問題も出題されていました。
2026年以降も同様の傾向になることが考えられます。
学校の進度より早めると相当有利
コロナの影響を受ける前から、公立中学校では社会を教え切るタイミングが学校ごとに異なりました。
公民や国際といった分野の出題量・重要性が高まる近年では、学校の進度と同じスピードでは十分な対策ができません。
学校の定期テスト対策などをしてくれる地元の補習タイプの塾も同様の傾向です。
家庭教師など、学校の定期テストの速度に捉われない指導をしてくれる先生がついていれば相当有利になります。
地理は地図と、歴史は現代が大切
地理(Amazonリンク)は様々な要素と組み合わせやすく、歴史よりはるかに実感が得やすい科目です。
また、1年生で多く扱うこともあり、復習が不十分になりやすいです。
中学1年生から正しい社会の勉強をしていれば、3年生になった際の復習は最低限で大きな効果が得られます。
社会が苦手、勉強法がわからない、点数が取れない生徒は、いい先生がいれば取り組み方や考え方、社会人になった後への活かし方まで様々な面で変わるでしょう。
社会は大切な科目ですが、地理は日常生活や経済と絡めて考えると楽しさが倍増します。
2024年は石川県の能登地方を中心とした地震から始まりましたが、お子さんはすぐに石川県の位置が頭に浮かんだでしょうか?
2025年は大阪万博が大きなニュースでしたが、大阪をはじめとした近畿地方の位置はすべてわかるでしょうか?
地図を頭にいれる
地理分野では、日本地図(Amazonリンク)と世界地図を頭に入れているかで大きな違いができます。
単純暗記ではなく、理解を交えながら地図を知ることが地理で平均点以上になるための必須条件であり、地理が楽しくなる第一歩といえます。
10年前より世界地図の理解度が重要視されています。
ロシアやウクライナ、中国の状況からもわかるように、主要国だけでよいので頭にいれておきましょう。
一歩上を目指したい生徒は、注目度が高まっている中東も少し覚えておくと、地理だけでなく国際ジャンルの出題にも対応しやすくなりますし、日々の勉強も楽しくなりやすいです。
歴史は近現代が頻出
年によって多少の差がありますが、近現代が大問の一つを占める可能性が非常に高いです。
高校でも2024年入試の新課程から近現代を重視する歴史総合が新設されており、高校1年生では必須の科目となっています。
歴史の大問が2つの時は、
近現代から一つ
それ以前から一つ
の可能性がとても高くなります。
近現代はペリーによる開国以降の話ですが、ドラマやアニメなどの舞台にもなりやすく、お子さんが興味を持ちやすいです。
歴史になかなか興味が持てないお子さんの場合は、古代や縄文弥生からではなく、近現代から歴史の勉強をスタートさせましょう。
縦軸の出題が増加
昔ながらの日本史(歴史)学習には、10年幅くらいで起こったことをまとめて覚えることが当然でした。
現代では、一つの時代とその前後の関連性が重要視されており、5~20年くらいや一つの時代での区切りをつけすぎる学習はおすすめできません。
実際に2024年の大問5では、日本の経済をテーマに近現代の100年近くを問う大問が出題されました。
2023年は日本医学の歴史がテーマで、約170年(江戸・明治・大正・昭和・平成・令和)を一気通貫して出題されています。
暗記に捉われるからつまらなくなる
千葉の入試は、知識系の問題は6割くらいです。
歴史は知識も当然必要ですが、細かい知識が不足していても平均点は簡単に超えることができます。
中学2年生~3年生の1学期で歴史を勉強しますが、定期テストなどの点数に惑わされず、歴史の流れを追う楽しさを知るところからはじめましょう。
私の授業でも、まずは歴史や地理など社会の要素を楽しむことからスタートする生徒が多く、楽しいと自然と自習時間が伸びて成績にもつながります。
公民と国際社会の重要性が高まっている
国際化と現代の政治情勢を重要視しているのが、千葉県の公立高校入試。
国際分野、経済分野からの出題が多くなっています。
こどもNISAやこども家庭庁など、お子さんに直接かかわる政治・経済政策が増えたこともあり、中学生が公民を学ぶ重要性は極めて高いといえます。
よくある質問・料金などは → こちら
プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら
データは理解して読み解く
貿易や紛争、情報化など様々なデータに関する出題があります。
データに関する事前知識がある程度あれば有利にはなりますが、知識が不十分でもデータを正しく読み解ければ確実に点数が取れるように作られています。
「データを正しく読み解く」ということは、国語や理科でも同様の能力を求められる出題があり、英語でのメールやポスターといった問題も本質的に同じです。
3分野でも最も暗記が少ない公民は、最も思考力が必要な分野といえるでしょう。
ただし、国際分野の出題量が増えるなど、公民の分量が増えているので計画性は以前よりも重要です。
少しずつで構わないので、早くからスタートすればするほど確実に有利です。
国際問題は地図がわかっていなければ何もできない
現代の国際問題は、主要国の地理的関係がわかっていないと理解できません。
地理でも、日本地図に加えて世界地図が大切だ。
という話を書きましたが、公民ではさらに重要になります。
![]()
1年生のときにあまり覚えられなかった、復習が不十分なあなた。
3年生にも復習チャンスがあります。
保護者の方も、お子さんと一緒に世界地図を書くチャレンジをしてみると楽しいですよ。
参考書・問題集
参考書で注意すべきが、厚さです。
社会が得意だったり、好きなお子さんの場合には、分厚く1冊で3年分が入った参考書(Amazonリンク)がおすすめです。
重いので家に参考書を置いて、問題集よりも参考書と触れ合う時間を長くしやすい環境がベスト。
iPadなどのタブレットは、うまく使いこなせる子にとっては有効ですが、多くの子にとっては使いにくいようなので、注意が必要です。
社会が苦手なお子さんは、分野別の参考書や問題集(Amazonリンク)をおすすめします。
持ち運びもしやすく、学校の授業の際にも教科書と並べて勉強したり、教科書よりわかりやすいので、教科書より参考書をメインで勉強することも、効果があります。
問題集
千葉の入試には標準レベルの問題集や、3年分を網羅的に復習(Amazonリンク)できるものがよいでしょう。
問題が解けたかどうかではなく、良質な復習ができるかがポイント。
間違えた問題や、気になった部分を、地図帳や資料集を使いながらしっかり復習することが、合格への近道です。
過去問を解くのは全範囲が終わってから理想ですが、学校の学習そのものが遅れていたり、お子さんの復習に遅れがあると、過去問を解く時間がなくなります。
理想をいえば中3の夏に一度解いておくだけで意識が変わりやすくなります。
現実には、早くて秋ごろ、遅くとも12月~1月には少しずつ解き始めるのがよいでしょう。
まとめ
- 思考力がポイント
- 公民が合否のカギ
- 身近で興味が最優先
保護者の方へ
中学の社会では、「思考力」と「国際化」がここ10~20年くらいのポイントとなっています。
千葉県でもその傾向が強く、特に公民の出題比率が増加傾向にあります。
もはや公立でも学校だけでは不足が大きくなる時代。
自習で積極的に分析ができていれば問題ありませんが、お子さんが自己分析や問題分析に自信がない場合は、塾や家庭教師などを用意することをおすすめします。
高校受験や中学生のお子さんの勉強に関する相談は → こちら
よくある質問・料金・web(オンライン)指導などは → こちら
他の記事一覧は → こちら