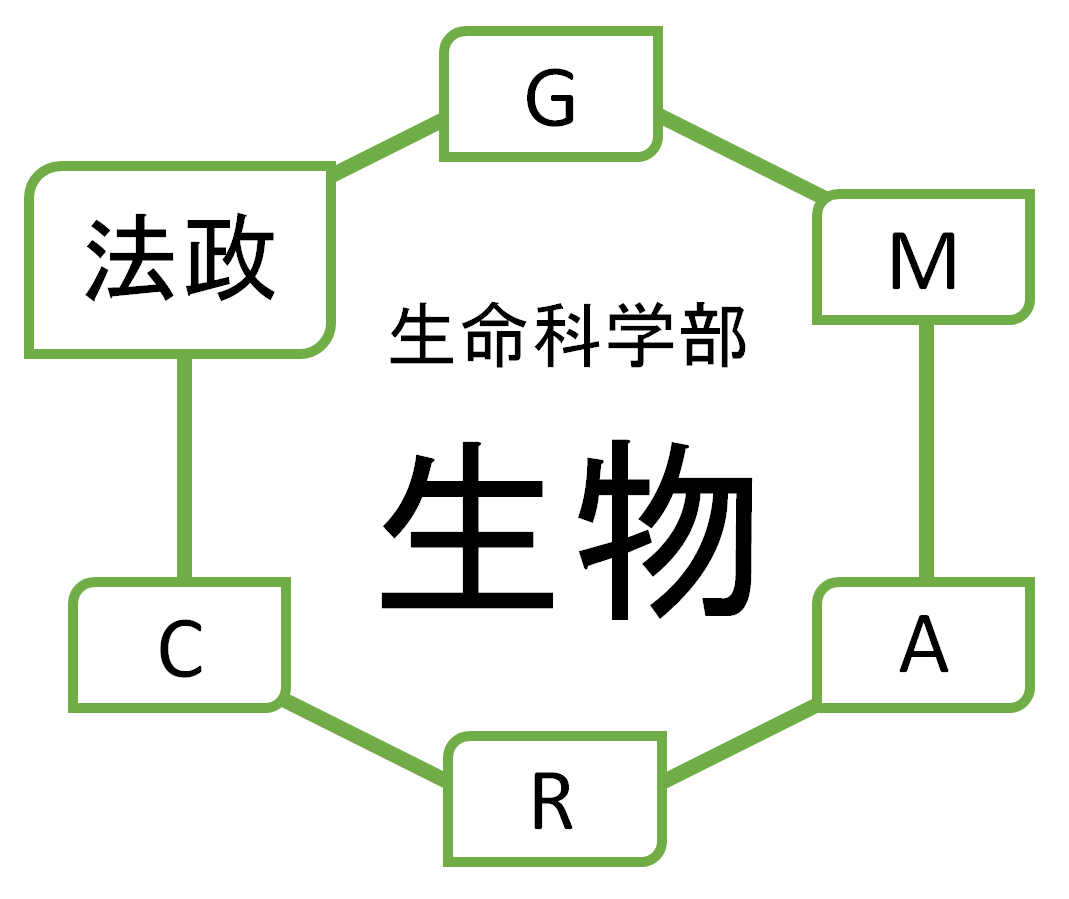上智大学 理工学部の数学
最も定員の多い共通テストとの併用型は、
共通テストでも数学が60点。
独自試験でも数学が100点。
理科と並んで最重要科目となっています。
また、TEAP利用型(Amazonリンク)は全学部統一。
理系数学は理工学部と経済学部で使われます。
ここでは、理工学部のみの試験である共通テスト併用型の数学の解説になります。
2025年は移行期間
2025年1~3月の入試は新課程への移行期間
理系数学の範囲はⅠAⅡBⅢCですが、
Bは数列
Cはベクトル
からしか出題がありません。
2026年以降はおそらくBとCも全範囲になるでしょう。
形式は一般的
大問は3~4つあります。
マークシート形式なので桁数などがわかり、取り組みやすいです。
ただし、最後の大問は完全記述で証明や図示が出題されることもあります。
大問1は小問集合の年も大問になっている年もありますが、現在は3つの小問集合が主流となっています。
他の理工学部・理学部分析 → 立教大学 学習院大学 中央大学 日本女子大学
四工大分析 → 芝浦工業大学 東京都市大学 工学院大学 東京電機大学
数Ⅲが最重要
過去問(Amazonリンク)の傾向をみると大問の2~3つは数Ⅲから出題されるます。
実際に勉強の中心は数Ⅲとなるでしょう。
現役合格を目指すのであれば、数Ⅲまでの問題集を遅くとも2学期前には1回は解ききっておきたいです。
2年生の冬休みと春休み、3年生の夏休みの使い方も重要になります。
上智の難易度を考えると、中高一貫校のように早めの対策をしなければ浪人も十分に視野に入ってくるでしょう。
微積は典型的な問題が1問
3~4つの大問のうち、1つは確実に、場合によっては2つ微積が出題されます。
2016年以前は2つが多かったですが、2017年以降の傾向では微積がメインは1つが多いです。
2022年は微積比率が低かったですが、2023年は2つの大問で微積でした。
微分では最近は2,3次関数や円の微分、分数関数の微分が比較的よく出ており、少し前は対数、三角関数の微分の出題頻度が高かったです。
微分積分の問題自体は比較的典型的で、標準的な問題集をやりこむことで十分に解決ができます。
面積だけでなく体積が非常に頻出。
空間をとらえるためには、十分な練習が必要です。
他の分野もある
双曲線と楕円や、複素数平面の極座標など数Ⅲは全般的に出題されます。
これらの分野は単独で出題されることもありますが、
数Ⅰ、Ⅱなどと複合で出題されることもあるので、注意が必要です。
BとCも根本から理解する
数列とベクトルも、どちらかがほぼ毎年出題されます。
2025年は移行期間ということもあり数列とベクトルのどちらかが出る可能性は高そうです。
数列では漸化式
ベクトルでは空間ベクトル
どちらも典型的なパターンがありますが、
数列では基本的な等差数列と等比数列の原理を理解した上で、漸化式の意味を理解してパターン学習をします。
空間はベクトルでも微積でも出題されやすい
空間ベクトルは、まずは平面ベクトルを極めること。
空間ベクトルなんだから、平面はいらないと勘違いしている生徒が非常に多く見られますが、平面ができなければ空間はできません。
逆に、平面ができれば、空間は楽勝です。
![]()
さらに余裕がある生徒、数学が得意で点を稼ぎたい生徒は、
空間を図形で処理する方法
図形ではなく計算で処理する方法
のどちらもマスターできると、合格率がさらに高まります。
プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら
オンライン(ウェブ)授業のご説明は → こちら
全記事一覧は → こちら
Aからも頻出分野はある
Aでは確率は非常に頻出。
とくに数列との組み合わせは王道であり、よく問われます。
また、マークシートということもあり、数学と人間の活動(整数の性質)の出題頻度は非常に低くなっています。
数ⅠAⅡは基礎原理を理解
この範囲はAの確率を除いて、出題比率が圧倒的に低いです。
逆に確率は非常に出題されやすいので、確実に対策をしておかなければいけません。
一方で、双曲線と楕円の範囲では、数Ⅰの2次関数や数Ⅱの図形と方程式などが非常に重要。
この範囲の微積の出題傾向が近年高くなっているので、数Ⅲのために数Ⅰや数Ⅱの勉強は必要となります。
数Ⅲの微分では三角関数や対数関数は、頻度は高くありませんが、出題されたことはあります。
そういう意味でも数Ⅱの三角関数や指数対数は基礎をしっかりおさえておきましょう。
対策・勉強法
受験勉強の中心は数B・Cと数Ⅲになりますが、基礎をおろそかにしてはいけません。
共通テストが一定程度(最低でも安定して60点以上)できる実力があって初めて、上智の対策がスタートできます。
問題集
問題集のレベルとしては黄色チャート(Amazonリンク)では少し不足。
青チャート(Amazonリンク)やフォーカスゴールド(Amazonリンク)では一部の問題は難易度が少し高いです。
数Ⅲの微分積分や極限を理解するためにも、数ⅡBは確かな実力が必要です。
数学にそこまで自信がない人は、数ⅠAと数ⅢCでは黄色チャート、数ⅡBでは青チャートくらいがいいでしょう。
ただし、これでは合格最低点レベルである60~70%の学力は得られますが、満点に近い学力は難しいでしょう。
問題集は繰り返し
難関私立である上智の理工の数学は、はっきりいって難しいです。
問題集を解く前に、ひとつひとつの公式をしっかり導けるようにならなければいけません。
特に数Ⅱレベルの微積や数Bの範囲は深い理解が必要であり、理解をしてから問題を解きましょう。
浪人生などでよく見られる失敗ですが、公式な定理をきちんと理解せずに、問題演習ばかりをする生徒がいます。
これは間違いです。
上智クラスには、それでは合格できません。
まとめ
- 数BCと数Ⅲのために、基礎理解をしよう
- 空間のためには、平面が必要
- 難しいからこそ早めの準備
保護者の方へ
上智レベルとなると、数学は非常に難しく、2022年のような共通テストの変化でも対応できる本質的な学力が必要です。
また、2025年は旧課程との移行期間ですが、2026年からは完全に新課程のみ。
独自試験は共通テストよりも大きく難しいので、現役で合格するのであれば最低でも高校2年生の夏には受験生としての自覚をもって勉強を進めましょう。
逆に言えば、高2の春~夏くらいから真面目に勉強をしていれば、部活にかなり熱中していても文武両道で合格まで到達できます。
保護者の方が場合によっては塾や家庭教師を利用しながら、綿密なコミュニケーションを日々とることをオススメします。
私の生徒でも、進路や大学に関する話は、高校1年の間にも複数回行ぅており、早め早めの準備が最も効果的です。
成績を大きく上げて上智大学の合格を目指すなら → こちら
他の記事一覧は → こちら